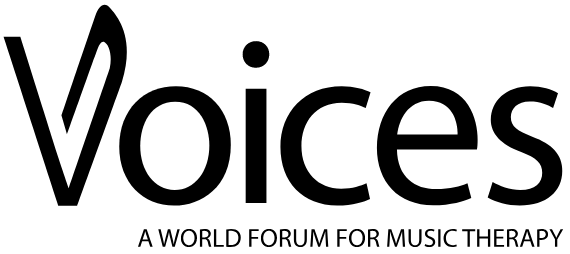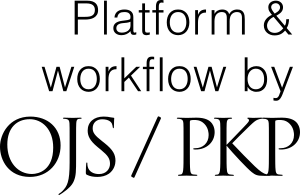音楽の中で共にいること:
哲学カフェでの対話を通じた一考察
Abstract
本論の目的は、重度重複障害のある青年を対象とする音楽療法セッション事例から生じた問いを、事例に直接関わりのない人々と共有・対話する試みについて報告し、その意義を振り返ることである。
セッション開始当初、私は「クライエントとどうやって一緒に音楽できる?」という問いを抱いた。私は、この問いがクライエントとセラピストである私との二者関係に閉じているのではなく、より大きな社会の構造のなかにあって、そこでの様々な価値観や関係に結びついていると直観的に感じた。そこで私は、事例に直接関わりのない人々とこの問いを共有すべく、哲学カフェという手法を用いて小さな対話のイベントを行った。ここでは、参加者がお互いの見方の違いを味わい、新たな見方を一緒に発見することを通して、そこで論じられた言葉のイメージを共有するプロセスが生じていたと思われる。
この試みは、臨床実践の現場とそれを取り巻くコミュニティをつなぎ、事例を社会にひらいていく例のひとつとして参考となるだろう。また、このような対話を通じて、ある言葉や概念をじっくりと吟味し、そこにある差異を細やかに感知していくことは、近代西洋中心的に発展してきた音楽療法領域における言葉や概念の使用を見直すことにもつながるだろう。
はじめに
この論考は、重度重複障害のある青年との約7年間の個人音楽療法についての、進行中の事例研究の一部である。セッション開始当初、私1は「クライエントとどうやって一緒に音楽できる?」という悩みを抱いた。臨床プロセスを詳しく検討するにつれて、私の悩みが「背景や価値観の違うクライエントとセラピストが一緒に音楽するってどういうこと?」という、より普遍的な問いへとつながっていることに、次第に気づくようになった。私には、この問いをクライエントと自分の間に留めたままではいけないのではないかという直観があった。なぜなら、クライエントと私との関係は二者関係に閉じているのではなく、より大きな社会の構造のなかにあって、そこでの様々な価値観や関係に結びついているからだ。私は、この問いを事例に直接関わりのない人々とも共有したいと考え、小さな対話のイベントを行った。
本論文では、この試みの検討を通じ、実践から生まれた問いを事例に直接関わっていない人と共有することの意義について考えることを目的とする。本論文の構成は、次の通りである。1.では、事例の概要と私が問いを抱いた経緯を述べる。2.では、このイベントで用いた哲学カフェという対話のスタイルの概要を示す。3.では、イベントで対話がどのように進んでいったかを詳述する。4.では、この試みから見出されたことを振り返り、その意義について考察する。最後に、このような対話の試みが音楽療法領域の発展にどのように貢献できるかについて触れる。
1.事例の概要2 セッション初期に私が抱いた問い
クライエント(Cl.)は、 重度の視覚障害, 知的障害, 身体障害を併せ持つ青年。本論の公開にあたり、クライエントの個⼈情報とプライバシーの保護に配慮し、家族から同意を得た。また、対話の参加者個人が特定されないよう配慮した。5歳より現在のコ・セラピスト(Co.)が主セラピストとして個人音楽療法を開始。12歳の時に私が主セラピスト担当を引き継いだ。以降、Cl.が特別支援学校高等部を卒業するまでの7年間、隔週1回のセッションを行った。セッションは、歌唱や即興の活動を含む、Cl.が自分なりの発達の道を歩むことを促進するクライエント中心・リソース指向のアプローチだった。
セッション初期のころ、私が抱いた悩みは「どうしたら、彼と一緒に音楽できるのだろう?」だった。当時のCl.には、前任の音楽療法士と一緒に約7年間かけて作ってきた、遊び歌や若者向けのポピュラー・ソングのレパートリーがあった。彼は毎回それらの歌を歌ったが、私が何か新しい活動や提案をしようとするとすぐに「おしまい!」と言った。彼の「おしまい」には、音楽療法士が代わったことへの緊張、新しい活動が彼の認知的・心理的状況やニーズに合わないという表現、自律性を育むための発達の過程のひとつといった様々な理由が考えられたが、その時は確かなことは分からなかった。私は、ただ彼の行動の表面を見て、活動の拡がりにくさを感じていた。また、彼のレパートリーを一緒に歌うときは、麻痺のある彼の身体がどのように音楽を感じ表現しているのかを掴むのが難しく、私は音楽の流れにうまく乗れないと感じることが多かった。そこでは、単に私が彼に合わせて一緒に歌おうとしているだけのようで、彼と一緒に音楽をしているという実感を持つことが難しかった。つまり私は、Cl.と「音楽の中で共にいること」に課題を抱えていたのである。
試行錯誤を繰り返すうちに、私は、Cl.と私のあいだにある、〈音楽〉をめぐる意図や認識のずれに気づいていった(表1)。Cl.は、始まりと終わりが明確で、時間の区切りが短い音・音楽に慣れ親しんでいる。それに対して私は、Cl.が好む音やフレーズ、ポップソングのモチーフやレパートリーを発展させたいという思いがあった。その思いは、私がセラピストとして望む音楽的発展だったが、その裏には、すぐに終わってしまったらどうしていいかわからない、たんに繰り返すだけではセラピストとしての能力や技術が足りないのではないか、などの個人的な不安が潜んでいた。つまり、互いの〈音楽〉のずれに着目することで、私は、セラピストとしての私の欲望とその奥に潜む本音、言い換えれば、自分の感覚や思考の偏りに気づかされたのである。
事例を検討するにつれて、私は、「Cl.と一緒にどうやって音楽できる?」という悩みが「そもそも背景や価値観の違うクライエントとセラピストが一緒に音楽するってどういうこと?」という普遍的な問いへとつながっていることに、徐々に気づいていった。私はこの問いを誰かと共有し、さらに探求したいと思った。より正確にいえば、この問いに向かいあわなければ音楽療法士としての自分が立ち行かなくなってしまうような切迫感を感じていたのだ。通常、事例から生まれた疑問や悩みを共有するには、たとえば、ある症例について問題点や解決方法を話し合う事例検討会や、専門的な実践家として成長するために音楽療法士どうしでサポートし合うピア・スーパービジョンがある。しかし私は、単にセッションの改善策を求めたり専門家として進むべき方向を模索したりするのとはもっと別の方法で、自分の問いを探る必要があると感じていた。後から振り返ってみるとそこには、私がクライエントとの間で感じた「ずれ」やそれに伴う違和感を、クライエントと自分の間に留めたままではいけないのではないかという直観があった。なぜなら、クライエントと私との関係は二者関係に閉じているのではなく、より大きな社会の構造のなかにあって、そこでの様々な価値観や関係に結びついているからだ。そこで私は、この問いを事例と直接関わりのない立場や視点の異なる人に開きたいと考え、小さな対話のイベントを企画した。
2.対話の方法:哲学カフェ
対話のイベントでは、「哲学カフェ」という手法を取り入れた。哲学カフェとは、対話の交通整理をする進行役のもと、ひとつのテーマについて集まった人たちで一緒に探求していくことを目的に、話し、聞き、語る場である(鷲田他, 2014)。1992年にフランスの哲学者マルク・ソーテが「カフェ・デ・ファール」で始め(ソーテ, 1996)、その後活動が世界に広がっていった。日本でも、様々なテーマで様々な場所で開催されている(例えば、鷲田他, 2014, 323-339)。
哲学カフェにおける対話の目的は、ものごとについての合意形成や問題解決ではなく、問いの発見、問いの更新である(鷲田他, 2014, p.ⅲ)。ここでの問いとは、「知らないことを知るための問いではなく、知っていることを改めて問う」(同書, p.44)ことである。重要なのは「物事や相互の理解を深めたり、疑問をもったり、背景や前提を探ったり、といった探求のプロセスそのものであり、それを共同で行うこと」(梶谷,2015, p.102)だという。
哲学カフェのやり方には、スタンダードや定型があるわけではない。基本的に、そこに居合わせた人々による一回的な集まりである。参加者は自己紹介等をする必要はなく、出入りも自由だ。ただし、他者と共同で対話を深めるための、参加の基本的なルールや姿勢がいくつかある。ここでは、梶谷(2015, p.102-106)を挙げておく。彼によれば、これらは思考と発言の自由を尊重し、それを支える「知的安心感」(intellectual safety)を確保するためのルールである。
-
何を言ってもいい(つまらないこと、流れからそれていることなどでもよい)。
-
他の参加者やその発言を一概に否定するような発言はしない。むしろ、その発言がどのように出てきたのかという前提を探る。
-
発言せずに、ただ聞いて考えているだけでもいい。
-
お互いに問いかけることが大切。
-
誰かが言ったことや本に書いてあることではなく、自分の経験に即して話す。
-
結論が出なくても、話がまとまらなくてもいい。
-
分からなくなってもいい。
哲学カフェでは、テーマに沿って、他者の話をじっくりと聞き、その時々で自分が考えたことや感じたことを自分の経験に即して語ることが求められる。参加者の語りは必ずしも首尾一貫している必要はなく、また前の人の語りを受けて話さないといけないわけでもない。途切れ途切れでもよいし、対話の途中で自分の考えが変わったり、わからなくなったりしてもよい。哲学カフェでは、そのような「自分が当たり前と思っていることが揺らぐ経験」が大事にされる。つまり、それぞれの参加者が自らの当たり前としている視点に気づき、他者の視点を組み入れて新たな視点から物事を捉えることが重要である。対話の進行役は、参加者の語りを助けたり、語られたことの意味が明確であるかを他の参加者に尋ねたり、発言者どうしの意見を関連づけたりして、対話を促進する「交通整理」のような役割を果たす。時には進行役も一緒に道に迷いながら対話が進められる。
3.対話の実際
セッション開始から数年間を経て、対話のイベントが行われた。参加者は募集に応じて集まった約10名で、音楽療法士、音楽家、対話に興味のある人などがいた。全体は2時間ほどのイベントで、私たちはとある一室に車座になって座り、語り合った。前半は、私が自分の事例から問いを抱くに至ったプロセスを話した。後半は、進行役のファシリテートのもと、参加者全員で対話を行った。後半では私は、いち参加者として対話に加わった。進行役は、音楽療法士ではない、哲学カフェの実践を行っている知人が務めた。この対話イベントは、もともと事例研究の一環として計画されたものではなかったので、開催にあたりCl.の家族から事例を共有する許諾を得た。Cl.に関する情報の説明は最小限にし、私が疑問を抱いたプロセスを自分自身の経験から語ることに集中した。
以下に、イベントで行われた対話を記述する。この記述は、音声記録をもとに、参加者の発言を私が再構成したものである。加えて、参加者の発言を整理する進行役の発言を参照している。この記述は全て、対話の中で参加者と進行役によって語られた内容であって、後から私による解釈やまとめを加えてはいない。ただし、私が参加者のひとりとして発言した内容は記述に含まれている。
対話の流れ
対話では、まず、前半の事例の話を聞いて思いついたキーワードを参加者が一つずつ挙げ、そのキーワードを用いてたくさんの問いを出し合った。その中から、「共に感じることと寄り添うことは違うのか?」という問いを選び、このテーマに沿って対話を行った。
はじめに、進行役が「テーマに含まれる“共に感じる”“寄り添う”という言葉から、どのような経験を思い起こしますか」と問いかけた。参加者はそれぞれ思いついたことを語った。
これらの発言を通じて、“共に感じる”に必要なのは、誰かとコンテクストを共有していることや何かを一緒に経験することであり、(相手への)共感や理解とは少し異なるらしいことが見えてきた。
次に、“寄り添う”という言葉についても同様に、それぞれの考えを出し合った。
「たとえば、生まれたばかりの子どもと母親のことを考えた時、全く一体化している状況では、“寄り添う”という言葉を使わない。人と人とのあいだにずれがあるからこそ、“寄り添う”ことを感じられるのではないか」。
「しかし、寄り添われる側は“寄り添われる”とは言わないし3、迷惑に思っていることがあるかもしれない」。
これらの話から“寄り添う”とは、立場の違いや上下関係が前提にあって、相手へのサポートや気遣いをすることが含まれるらしいことが見えてきた。
そして、「“共に感じる”ことと“寄り添う”ことは違うのか」という冒頭のテーマに立ち返り、違うとすればどこが違うのか、違わないとすればどこが違わないのかについて、さらに語り合った。
すると、これまで出された“寄り添う”の意味合いが少し変化するような、次のエピソードが語られた。
この発言を受けて、その場の空気感が変わり、こんな発言も出てきた。
さらに、次のような語りも生まれてきた。
終了後の参加者アンケートでは、以下のような感想があった。
4.対話の試みから見えてきたこと
ここまで、私が音楽療法事例で抱いた問いを臨床現場にいなかった参加者に共有し、対話する試みについて述べてきた。ここでは、対話によって何をしていたのか、それにはどのような意義があるのかについて、考察を試みる。
事例とそのコンテクストに含まれるさまざまな差異
まず、ここでの対話が何をめぐって行われていたかを考えてみたい。試みを振り返って見えてきたのは、人々の多様性とそれを区分けする差異の問題4ではないかと思われる。
私たちが暮らす現代社会には、多様な人々がいて、多様な生き方がある。社会には、人種、能力、労働、住処、ジェンダー・セクシュアリティといった要素によって、様々な差異がある。たとえば、病/健康、障害/健常、異常/正常、少数/多数、女性/男性、被害/加害、など。人々は、これらのカテゴリーによって区分され、関係づけられる。どこに線を引くか、どの立場から見るかで、まったく違った風景が見えてくる。この差異は、時に孤立や分断、生きづらさを生じさせることもある。差異によって隔てられた人々の関係を変えていくためには、不利な立場にある側の声を聞き、彼らの社会参加の権利を保障することはもちろん重要である。しかし同時に、多様な立場の人たちの視点を持ち寄って、一緒に差異について考えていくことも必要だと思われる。
事例に即してこのことを考えると、Cl.と私の間には、治療やケアに関する役割の違い(受け手/与え手)、音楽に関する経験の違い、さらに年齢や性別の違いといった様々な差異がある。もちろん、セッションでは表面化しないさらに複雑な差異もたくさんあるだろう。このことを踏まえれば、「異なる背景や価値観を持つクライエントとセラピストが一緒に音楽するってどういうこと?」と問うことは、音楽療法セッションとそのコンテクストを取り巻く様々な差異を意識化することだと言えるだろう。したがって、この問いをめぐって事例に直接関わっていない人々と対話することは、立場や経験の異なる多様な人々が互いの見方を持ち寄って、そこにある差異について考えることだと思われる。
差異について考える対話
では、実際の対話では、そこにある差異がどのように扱われたのだろうか。この点について、今回のイベントで特徴的だったと思われる対話の設定や進め方との関わりから述べる。
まず、ここでの対話の特徴として挙げられるのは、事例から生まれた問いを直接のテーマにして話すわけではなく、そこから生まれたキーワードをもとに参加者によって新たな問いが立てられ、そのテーマに沿って対話を行った点である。もし、事例から生まれた問いについて参加者が直接対話すれば、事例に関わる差異や不均衡な力関係がそのまま対話に持ち込まれるだろう。音楽療法に携わる人々は、この事例をどう発展させるべきかについて職業的専門性の見地から語るかもしれないし、音楽療法に携わっていない人たちは、知らなかったことを教わることに徹するかもしれない。あるいは、自らを“健常”の側にいると考える参加者によって、障害のある人の意図や権利をいかに尊重するべきかについて話し合われるかもしれない。しかしここでは、対話のテーマは事例から導き出されてはいるものの、参加者によって立てられたより普遍的な問い―「“共に感じる”ことと“寄り添う”ことは違うのか」-へと置き換えられている。このことによって、参加者は事例について第三者的な立場から考えるのではなく、「あなたにとって“他者と共にいる”ってどういうこと?」を自分自身のこととして考えることが求められる。つまり、このような設定によって、参加者が職業的専門性における立場や属性をいったん脇に置いて対話に参加し、人々の間にある差異を自分自身の経験に照らして考える機会になったのではないかと思われる。
もうひとつの特徴は、人々の差異と丁寧にコミュニケートするという、哲学カフェのスタイルである。日本における哲学カフェ実践の先駆者でもある哲学者の鷲田清一(2013)は、対話というコミュニケーションの本質を、「語り合えば語りあうほど他人と自分との違いがより微細に分かるようになること」であるという。このことを対話イベントに即して振り返ると、参加者は、“共に感じる”ことや“寄り添う”ことについて、異なる経験や視点から思い思いに語った。それぞれの語りは一見バラバラで、必ずしも前後の脈絡がつながっていたわけではない。しかし、互いの視点や経験を交換していくうちに、「そんな見方もあるのか」という気づきがふと生まれ、その言葉の持っていたイメージが次第に変化していった。そこでは、参加者が互いの見方の違いを味わい、新たな見方を一緒に発見することを通して、そこで論じられた言葉のイメージを共有するプロセスが生じていたと思われる。この対話によって、人々の間にある差異がなくなったわけではないだろう。むしろ、“共に感じる”ことや“寄り添う”ことへの見方の違いをめぐって人々を隔てる線を何度も引き直すプロセスそのものが、人々の間に新たな関係を作っていくことにつながったのではないだろうか。さらに、ここでの体験を参加者が持ち帰り、それぞれの日常生活に即して考え続けることで、彼らが接する他者とのあいだにも波及的に対話がもたらされるかもしれない。
私にとっての対話の意義
あらためて振り返ってみると、対話のイベントは、私が事例で抱いていた悩みや課題を「問い」へと深めていくターニングポイントのひとつになった。当時は、なぜこのような対話をする必要があったのか、対話の経験が臨床実践とどう結びついているのかが自分でもよく分かっていなかったので、この機会に振り返ってみたい。
上述したように、私が事例で抱いた「Cl.と音楽の中で共にいること」にかんする悩みは、それと向かいあわなければ自分が立ち行かなくなってしまうような切迫したものだった。そこには、Cl.と「共にいること」を大事にしたいという音楽療法士としての私の信念と同時に、そのことに難しさを感じる自分への劣等感や罪悪感もあった。表1「Cl.と私との〈音楽〉をめぐる認識のずれ」で示したように、Cl.と私の二分法的な視点から互いの差異を意識化したことが、かえって自分を追い詰める一因にもなった。
しかし、対話では、いったん自分の事例から離れて、“共に感じる”や、“寄り添う”という言葉がじっくり吟味されるのを聞き、参加者と一緒に考えることができた。ある見方に隠れていた別の見方を浮かび上がらせたり、ある側面と別の側面のつながりを発見したりするような対話のプロセスに参加しているうちに、「共にいる」ことに関する自分のこだわりが徐々に解きほぐされていくような感覚があった。それは、自分の見方を「あれか/これか」から解き放ち、「こうであってもいいのではないか」という実感に浸されていく体験だったように思う。これをきっかけに、自分のなかにあった「どのように“共にいる”のが望ましいのか?」という偽の問いは形を変え、文字通り「“共にいる”とはどういうことか?」という真の問いに目を向けられるようになった。つまり、問いをまっすぐに探求できるようになったのだ。私にとってのこの対話の意義は、私の問いを他者に聞いてもらい、さらに問いを育てていくきっかけをもらったこと、そして、そのように自分に問うことを可能にしたことにあった。このことは、自分の考えを安心して話せる場で他者と一緒に考えるからこそ、できたことだろう5。
その後、Cl.とCo.と私の音楽的=療法的コラボレーションは、ユニークに発展していった。もちろんこれは、長い臨床プロセスの中で起こったことであって、哲学カフェとの因果関係はないかもしれない。共にいることにかんする私の試行錯誤は、今も続いている。しかし今の私は、かつてのように相手のために(と思って)自分を否定することではなく、相手も自分も否定しないことが共にいることの基盤だということに気づいている。
5.おわりに
最後に、今回の対話の試みから得られた知見が、音楽療法という領域の発展にどのように貢献するかに触れておきたい。本論は、個人と社会との関係に注目してコミュニティ全体に変化をもたらそうとするコミュニティ音楽療法にとって、とくに役立つ視点があるのではないかと考える。「コミュニティ音楽療法のプロセスは、何をするか、どのようにするか、それがどのように進むのか、そして次に何をするのかを決める民主的なプロセスに、全員を巻き込む試み」(Ansdell & Stige, 2016, p. 604) という方法論の一部になり得るかもしれない。さらに、音楽療法におけるフェミニズムの視点、リソース志向やリカバリーモデルの音楽療法などにも共鳴するだろう。また、このような対話は、音楽療法の分野で使われている言葉や概念を注意深く検討することも可能にする。それによって、西洋中心的な近代音楽療法の視点から発展してきた言葉や概念の使い方を見直すことにもつながるだろう。
今回の試みは、事例から生まれた問いを共有するために行った、たった一回の試みに過ぎない。人々のあいだにある差異によって隔てられた線を揺さぶり、関係を変えていくには、実践および研究のあらゆるレベルやコンテクストにおいて、対話を続けることが必要だと思われる。
Notes
[2] この事例の初期のプロセスの一部は、Miyake(2014)で取り上げた。
[3] 「寄り添われる」は、「寄り添う」の受動形だが、実際にはこのような使い方はしない。日本語話者にとって「寄り添われる」という考え方が不自然に感じられるのは、日本語としてこの用法が不自然に感じられることと関連していると思われる。
[4] 多様性と境界に関する視点については、私が研究員として関わった社会包摂と表現活動に関するプロジェクトから多くの示唆を得ている(三宅, 長津, 井尻, 2016を参照)。
[5] 現在、私は生野里花さんと共同で、音楽療法士が自らの臨床経験から出発して研究の問いを立ち上げ、育てていくためのピア対話グループ「ここのわ音楽療法臨床研究対話会」を主宰している。ここでは、本稿で行った哲学カフェよりも直接的に互いの臨床実践について話しているが、対話の基本的姿勢は共通している。ここでの仲間との対話が、本稿の振り返り部分を書く上で大いに参考になった。ここのわのメンバー、とりわけ2021年の日本音楽療法学会学術大会自主シンポジウムで討論した生野さん、布施葉子さん、伊藤孝子さん、Simon Gilbertsonさんに、心より感謝する。ここのわ音楽療法臨床研究対話会:https://nlnmhd.wixsite.com/website/blank-28
References
Miyake, H. (2014). Bio-political Perspectives on the Expression of People with Disabilities in Music Therapy: Case Examples., Voices: A World Forum for Music Therapy, vol.14(3). http://dx.doi.org/10.15845/voices.v14i3.800.
三宅博子, 長津結一郎, 井尻貴子(2016).「アートとケアにおける研究とその視座―対話型実践研究を事例に」, アートミーツケア学会オンラインジャーナル, 7, 37-50. https://artmeetscare.org/wp-content/uploads/2017/03/3_H_Miyake_37_50.pdf
鷲田清一(2013). せんだいメディアテーク自主事業「対話の可能性」序文. https://www.smt.jp/dialogues/