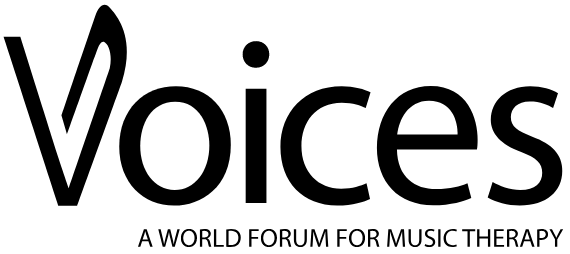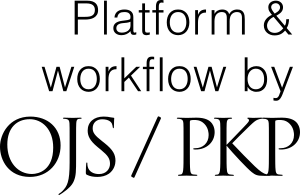生政治学の視点から音楽療法を再考する
今、ここでの我々は何者なのか、そしてここで何をしているのか? (Pavlicevic, 2004, p. 47)
概要 =
本論では、フーコー(1977、1990)、アガンベン(1998、1999)、ハート&ネグリ(2000、2004)による生権力や生政治の視点から、音楽療法プロセスの再考を試みる。
筆者の研究の中心的焦点は、音楽療法の政治的意味に関わるものである。このことについて本論では、Nordic Journal of Music Therapy誌に掲載された、エドワード事例の第1回目のセッションに関する議論を例に検討する。そこには、文化的に受け入れられる、ある特定の音楽表現へと向かう方向性が療法的意味と見なされているように思われる。ここで論じられている音楽的統合は、"行動の可能性"を増すものと捉えられているが、また一方で文明化(社会的適合)のプロセスでもあるだろう。生政治の視点から見ると、これまでの議論は専らビオスbiosの側、すなわち文明化の側から論じられ、ゾーエの側、すなわちクライエントの生そのものからの視点が欠けている傾向があったのではないかと考えられる。
音楽療法を通じた文化的統合は、果たして本当にクライエントのアイデンティティ構築を援助するものなのだろうか?本論では、このような問いをさらに探求するために、ハート&ネグリによるマルチチュードmultitudeの概念を紹介する。これは、音楽表現の特異性を尊重する新しい音楽作りのあり方を追求する上で示唆を与えるものであり、近年の多くの音楽療法士達の考えに呼応するものと考えられる。
はじめに
この数十年来、欧米における音楽療法は、専門的な資格教育による専門領域として確立されてきた。そこでは、音楽的介入の効果に関する証拠が必要とされ、科学的なパラダイムの枠内で、クライエントの背景の理解や様々な治療モデルと関連付けた音楽的プロセスの解釈等が追求されるようになった。これに対して、コミュニティ音楽療法や文化中心音楽療法のようなコンテクストに基づいたアプローチが、近年国際的な議論になってきている。
筆者は、重度の障害を持つ人達との音楽療法に携わるうちに、科学主義と文化主義という二つの視点のいずれにも何かしら充分ではないものを感じるようになった。そして、この問題は科学主義か文化主義かという二項対立よりもっと手前の基本的なところにあるのではないかと考えるようになったことが、本論の背景である。
筆者の研究の中心的焦点は、音楽療法の政治的意味に関わるものである。これは、音楽療法における最も基礎的な問題であると考えられる。本論では、フーコー、アガンベンらによる生政治学の視点から音楽療法プロセスを再考したい。筆者はこの議論が、文化中心音楽療法やコミュニティ音楽療法といった、コンテクストに基づいた音楽療法をさらに発展させる一助となり得るものと考える。
文化から政治へ
昨今の音楽療法の議論において、社会文化的視点を持つことの必要性が高まってきている。例えば、スティーゲは音楽療法に文化の概念を導入し、音楽療法は文化を抜きにして考えることは出来ないと述べている(Stige 2002)。彼によれば文化とは、人間の共存を可能にし、調整するための慣習やテクノロジーの蓄積である(ibid., p38)。これは、文化が人間にとって助けとなるだけでなく、抑圧となるものであることも意味している。
コミュニティ音楽療法の中心的概念のひとつに“コンテクスト”がある。パヴリチェヴィックとアンスデルはコミュニティ音楽療法を、異なる時に、異なる場所で、異なる人々の為に行われる異なるものだとしている(Pavlicevic and Ansdell 2004, p17)。これは、私達がこれ以上コンテクストや文化を考慮に入れることなしに音楽療法を考えることは出来ないことを主張するものである。このようにコミュニティ音楽療法の議論は必然的に、伝統的な音楽療法モデルの様々な矛盾を露わにした。アンスデルは、伝統的音楽療法の標準化された概念や手続きを“音楽療法のコンセンサスモデル”と呼んで批判した。
またアンスデルは、音楽療法を言説の束であると捉える(Ansdell 2003)。彼によれば、音楽療法は発見されるのではなく作られるものであり、私達が語る物語であるという。彼はこの議論により、音楽療法研究におけるメタ理論的視点の必要性を示唆している。
これらの相対主義的な見方のもとでは、音楽療法をより批評的に論じることが必要とされる。文化やコンテクスト、ストーリーは、一連の知や習慣によって構築され、蓄積される。知や習慣といったものは、規範や道徳を形作る様々な価値の束から成っている。日常生活で私達はあまりこのことを意識することはないが、それらは見えない政治の網の目のように張り巡らされ、私たちの生をコントロールしている。従って、音楽療法を社会文化的視点から論じようとするなら、政治的な視点からの議論が避けられないだろう。この問題はまだ十分に論じられてはいないが、筆者は、例えば文化中心音楽療法のようなコンテクストに基づいたアプローチを考える上で重要なものと考える。
生権力と生政治
生権力や生政治とは、近代以降の社会の仕組みの理解のためにフランスの哲学者ミシェル・フーコーによって提起された概念である(Foucault 1990)。
生権力とは一体何か? ここでの“権力”とは、無数の微細な力の関係である。この関係としての権力は到る所に偏在し、私達を取り巻いている。もちろん、音楽療法室も例外ではない。フーコーによれば、生権力とは人間の生の全ての側面に影響を及ぼすような統治の形態である。古代より主権者(例えば王)が行使して来た、死なせるか、生きるままにしておくかを決める権利(生殺与奪の権)は、17世紀以降、生きさせるか、あるいは死へと遺棄する権力に取って代わられた。このことは、生の支配の様式の変化を意味しており、新しい権力の特徴は、人々を“生きさせる”あるいは“生を育む”ところにある。
生権力は、次の二つの軸からなる。ひとつは、規律権力がつかさどる身体の解剖-政治学である。これは機械としての個人の身体に効力を及ぼし、従順な身体を作り上げる。有名な監獄の一望監視装置である“パノプティコン”は、この規律権力を具現化したものとして象徴的である(Foucault 1977, pp195-228)。もうひとつは、生物学的な種としての人間全体を焦点とする人口の生政治学である。これは、誕生、死亡、生殖、疾病といったものを管理調整する。
生権力とは、これら二つの権力技術を合わせて組織化したものである。ここでは、人間は個として、かつ(種)全体として管理される。私達が生きる現代社会は、標準化された規範や道徳によって取り巻かれ形成されており、これは管理コントロール社会と呼ばれることもある。フーコーは、この装置の皮肉は我々の解放がそこにかかっていると信じさせることだ、と述べている(Foucault 1990, p159)。以上が、私達の生と社会を巡る現在の状況のフーコー的見方であるが、そこからの出口を私達が見つけ出すことが出来るのか否かについては、様々な議論がある。
図1 生権力(Foucault 1990)

一方、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンは、生政治の概念を古代ギリシア以来の政治的力の本質的原理であると主張する (Agamben 1998)。彼は、ギリシアにおける政治を理解するのに、生を表す概念が二つに区別されていたことを取り上げ、探求の出発点としている。ひとつはビオスbios といい、社会的な生、あるいは共同体におけるある特定の生の形式を指す(共同体におけるある役割・機能・位置づけ)。もうひとつはゾーエzoeといい、自然的な生、あるいは生き物としての人間を指す。アガンベンはこれを“剥き出しの生”と呼んでいる。アガンベンによれば、政治的体制の構築は、政治的な生(ビオス)から剥き出しの生(ゾーエ)を排除することで、同時に政治的秩序の中に剥き出しの生を捕らえておくという、排除的包摂によって可能になった。
しかし近代社会においては、政治的な場にゾーエが包含され、政治の対象そのものになった、とアガンベンは主張する。これは“例外状態”と呼ばれるもので、排除されていたゾーエが政治の場に侵入することにより、外部と内部、排除と包含のあいだの不分明な地帯、グレイゾーンが生じる。彼によれば、現代社会はこのような例外状態が原則となり通例化した社会である。
ここでの生権力の働きは、剥き出しの生を始原的な政治的要素として、また自然と文化、ゾーエとビオスを明確に区別する境界線として生産するというものである。例えばアガンベンは、ナチスの収容所こそ近代の政治的パラダイムであるとしている。彼はフーコーに従いながら、人種主義とは生権力が人間の生物学的連続性に介入し、ついには剥き出しの生に到るまで分割するプロセスであると主張する(Agamben 1999, p84)。 言い換えればこれは分割と再編成を通じて生を操作し、私達自身の生の実感を奪うものと捉えることが出来る。
図2. 政治的体制における二つの生の概念 (Agamben 1998)

エドワードの事例:政治的な場としての音楽療法プロセス
ここでは、ノードフ=ロビンズによるエドワードの事例の第1回目のセッション(Nordoff and Robbins 1977)を取り上げ、音楽療法の場における生政治的側面について論じたい。
生政治的な視点から見てみると、音楽活動のプロセスは、ゾーエとビオスが出会う政治的な場であると考えられる。ここでは、ゾーエは音楽の生気性に関わっている。例えば、クライエントとセラピストの音楽的相互作用の説明にしばしば引用される生気情動 vitality affects(Stern 1985)は、ゾーエの側にあるものと捉えることが出来るだろう。ビオスは、音楽的構造や形式、イディオムといった、音楽の構造性に関わるものと考えられる。これは文化的に構築された音楽の意味と密接に関係する。上述したように、音楽の文化的意味は規範や道徳を形作る様々な価値の束から成る。従って、音楽的プロセスには、政治的な関係が不可避に介在するものと捉えるべきだろう。
この事例の焦点は、泣き叫んでいるエドワードと音楽療法士がどのようにして、音楽を通じて出会うのか、という点にある。仮にエドワードの叫びをゾーエ、セラピストの音楽的介入をビオスと捉えてみると、これはセラピストがエドワードのゾーエをビオスの領域に移行させ再編しようとするプロセスと解釈することが出来るだろう。そこでは、エドワードの叫びは単なる無秩序や混乱、カオスとして扱われ、音楽療法プロセスを通じて音楽的構造や形式のもとでコントロールされる。重要なのは、このプロセスを文明化と見なすことが出来る、という点である。
この事例は、Nordic Journal of Music Therapy誌上で複数の音楽療法士によって各々異なる視点から論じられている。しかし、そこには論者達に共有されているあるストーリーがあるように思われる。それは、エドワードの叫びが文化的に共有できるような音楽的表現へと移行したところに療法的意味を見出す、というストーリーである。例えば、ランディ・ロルフスヨルドは、この音楽的相互作用がエドワードに、より広い音楽的-文化的コミュニティにおける場所を与えたのだと主張する(Rorvsjord 1998) 。彼女によればこのことは、より広いコミュニティにおける音楽的-文化的メンバーシップの第一歩である。彼女は音楽療法が伝統的な音楽的イディオムまでも変えていく革命的な力を持つことを強調している。筆者は、彼女の主張に政治的視点が欠けているわけではないと考えるが、ここではしかし、より広い文化に参加する為に必要なある特定の能力が想定されているように思われる。ここでいう音楽的統合は、果たしてクライエントの“行動の可能性を増す” (Ruud 1998, p5)ものなのか、それとも文明化のプロセスなのだろうか。ここでは、音楽療法は文明化の側面に深く関わっているのではないかと考えられる。しかしそれは、私達の誰もが拒むことの出来ない音楽療法の機能のひとつと考えられているものだ。
生政治の視点から見ると、これまでの音楽療法の言説は専らビオスの側、すなわち文明化の側から論じられ、ゾーエの側からの視点が欠けている傾向があったのではないかと考えられる。そこでは、エドワードの生は“剥き出しの生”へと還元された上で、文化の中へと位置づけられ、統合される。エドワードの事例を巡る議論に参加している音楽療法士達は、表現のカオス的側面について慎重な態度を示しているが、彼らはそれを原初的なものから秩序へと向かう可能性として理解しているように見受けられる。このような方向付けはおそらく、音楽言語への依存によるものと考えられる。もし私達がカオスをゾーエの表現行為と捉えるならば、この文脈ではそれをある特定の意図や方向へ向けての出発点、つまり表現の可能性、としてではなく、それ自体としての潜在的可能性を秘め、意図や方向性から逃れた表現の《潜勢力potentiality》として理解するべきだろう。
音楽療法は誰のもの? マルチチュードの音楽療法へ向けて
現在、コミュニティ音楽療法や文化中心音楽療法のようなコンテクストに基づいたアプローチは、もっぱらビオスの側面から論じられることが多い。そしてそこには“音楽療法は誰のものか?”という疑問が生じる。これは、音楽療法の文化的視点に関する議論の重要性を否定するものではなく、さらに議論を発展させようとするものである。私達は自らに対して、次のように問いかけてみる必要があるのではないだろうか;音楽療法による文化への参加は果たしてコミュニティにおけるクライエントのアイデンティティ構築の助けとなり得るのだろうか?それは“力を奪われた人々”を作り出すこともあるのではないか?私達は文化的差異の強調によって、文化的“他者”を作り出してはいないだろうか?もしそうであるとするならば、これは “新たなコンセンサスモデル”ではないのか?
次の二つのモデルは、生政治の視点から見ると同じヨーロッパ中心主義の二つの側面に帰因することが出来る。ひとつは、人々を、標準化された“どこでもフィットする”モデルに還元してしまう“コンセンサスモデル”である。これについては、文化指向的な音楽療法のディスコースでしばしば論じられている。もうひとつは、その文化指向的な音楽療法が取り組む、文化的差異の問題の中にある。多文化モデルは、この問題を乗り越えることを期して登場したものであるが、ここには依然として問題が残っている。それは人々を(例えば障害者、移民などの)“異なる他者”として同定した上で新たな共同体倫理の中へ統合するという問題である。筆者がこれを “新たなコンセンサスモデル”と呼ぶのはこのためである。実際にはどちらのモデルも、同質性と差異性をはかる普遍的な基準として西洋のアイデンティティを参照している。それと同様に、音楽療法の多文化モデルは、自他が持つ音楽言語や音楽構造の同質性や差異性にばかり焦点を当ててしまう傾向があるのではないだろうか。このことは、構造や形式を重視する西洋的音楽学の考えと無関係ではないだろう。
では、どのようにしてこれを乗り越えることが出来るのだろうか?ここで参照したいのはアントニオ・ネグリとマイケル・ハートによる、マルチチュードmultitudeの概念である(Hardt&Negri 2004)。彼らは、生権力の現代的形象としてグローバルな新しい世界秩序が表れてきたとし、より広範に及ぶこのネットワーク的権力を帝国Empireと呼んでいる(Hardt &Negri 2000)。彼らによれば帝国は、帝国内部のヒエラルキーと分割を広める新しいグローバルな管理のメカニズムによって秩序を保つのだという。 アガンベンは現代世界を強制収容所として描いたが、ネグリとハートは私達全員が参加を強いられているグローバルな内戦状態であるとし、それに対し、世界への新たな参加の仕方を追求する必要があると主張する。この新たな世界の構築を担うのが、彼らがマルチチュードと呼ぶものである。
マルチチュードとは、このような現代の生政治的状況における潜在的な社会的主体である。ネグリとハートによればマルチチュードは、単一の同一性やアイデンティティに還元出来ない多数多様な内的差異からなり、異なる文化、人種、エスニシティ、ジェンダー、異なる生き方、世界観、欲望を持っている。従って、マルチチュードの概念が提起する課題は、いかにして社会的な多数多様性が内的に異なるものでありながら、互いにコミュニケートしつつ共に行動し、新たな秩序を自ら形成することが出来るのか、ということである。このようにして、私達の行うコミュニケーションやコラボレーションは、共同性を基盤にしているだけでなく、それ自体もまた新たな共同性を生み出す。これは、文化に隠された管理的政治による排除から人々を新たなネットワークへと再編しようとするものであり、このような問題を考える上での鍵となるかも知れない概念である。筆者は、このマルチチュードの考えによって、音楽療法のコンセンサスモデルと多文化主義を越える第三の道を追求したいと考える。
実際、マルチチュードの概念は、最近の多くの音楽療法士の意志に呼応するものと思われる。例えば、スティーゲの「音楽療法士は世界を変えることを通じてクライエントを援助することが出来る、たとえそれがほんの少しであっても(Stige 2002, p128)」という言葉は、音楽療法がなすべきことのなかに社会変革が含まれうることを主張している。またサイモン・プロクターも、音楽的参加を通じて生じる社会的資本Social Capitalに着目し、政治的取り組みとしての音楽療法の側面を強調している(Procter 2004, pp227-228)。彼の提示する、健康を促進する音楽的資本Musical Capital(ibid.pp227-228)は、マルチチュードの概念に適合するものと思われる。筆者はさらに、マルチチュードは新たな音楽的資本を創造するものと考える。
では、音楽療法においてクライエントとセラピストはどのようにして同じマルチチュードの一員たり得るのだろうか?ここには決まった答えは存在しないが、次のように言うことが出来るだろう。すなわち、音楽療法は必ず政治的行動であり、この問題から逃れることの出来る外部は存在しない。筆者はマルチチュードの考えを通じて、私達が特異性を尊重することで新たな共同性を生み出すような、新しい音楽作りの方向性を創り出していくことに期待したい。
参考文献
Agamben, G. (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life . Stanford University Press. [『ホモ・サケル:主権権力と剥き出しの生』、高桑和巳訳、以文社、2003]
Agamben, G. (1999). Remnants of Auschwitz: The Witness and Archive. Zone Books. [『アウシュヴィッツの残りのもの:アルシーヴと証人』、上村忠男・廣石正和訳、月曜社、2001]
Ansdell, G. (2003). The Stories We Tell: Some Meta-theoretical Reflections on Music Therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 12(2), 152-159.
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Penguin Books. [『監獄の誕生:監視と処罰』、田村俶訳、新潮社、1977]
Foucault, M. (1990). The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Vintage Books. [『性の歴史Ⅰ:知への意志』、渡辺守章訳、新潮社、1986]
Nordoff, P. and Robbins, C. (1977). Creative Music Therapy. the John Day Company.
Hardt, M. and Negri, A. (2000). Empire. Harvard University Press. Also available to read the full text on http://www.infoshop.org/texts/empire.pdf [『帝国:グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』、水嶋一憲他訳、以文社、2003]
Hardt, M. and Negri, A. (2004). Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. Penguin Books.
Pavlicevic, M. (2004). Learning from Thembalethu: Towards Responsive and Responsible Practice in Community Music Therapy.,In M. Pavlicevic & G. Ansdell (Eds.), Community Music Therapy (pp. 35-47). London: Jessica Kingsley Publishers.
Pavlicevic, M. and Ansdell, G. (Eds.) (2004). Community Music Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.
Procter, S. (2004). Playing Politics: Community Music Therapy and the Therapeutic Redistribution of Music Capital for Mental Health. In M. Pavlicevic & G. Ansdell (Eds.), Community Music Therapy (pp. 214-232). London: Jessica Kingsley Publishers.
Rolvsjord, R. (1998). Another Story about Edward. http://www.njmt.no/artikkelrolvsjord72.html
Ruud, E. (1998). Music Therapy: Improvisation, Communication, and Culture. Gilsum, NH: Barcelona Publishers.
Stern, D.N. (1985). The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. Basic Books. [『乳児の対人世界:理論編』、神庭靖子、神庭重信訳、岩崎学術出版社、1989]
Stige, B. (2002). Culture-centered music therapy. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. [『文化中心音楽療法』、阪上正巳監訳、音楽之友社、2008]