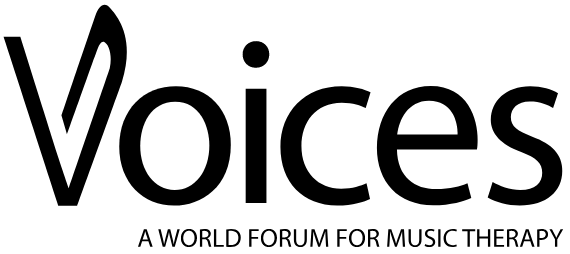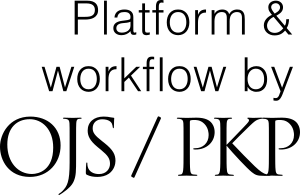[Original Voices: Genre]
重度知的障碍児との長期にわたる音楽療法セッションにおける
「意味深さの経験」に関する考察
By Rika Ikuno
はじめに
研究の背景
本稿は、ひとりの重度知的障碍児との6年にわたる音楽療法症例を題材とし、療法の場に参加している者たちによって経験される「意味深さ」の多層的側面とその研究方法を考えるものである。この研究の背景には、筆者がかねてより考えてきた以下のような視点がある。すなわち、音楽療法セッションという事象には、医科学としての「治療」や、対象者の既存社会への適応を目的とした「教育」や「訓練」など、介入-効果の構造からだけでは論じ切れないのではないか、そこには独自的な「意味深さ」の経験の広がりがあり、対象者及び療法士の参加の質に大きく関与しているのではないかというものである。その意味の広がりは、当然、介入-効果の構造にも大きな影響を与えており、本稿はそうした伝統的構造を批判しようとするものではない。むしろ、違った方向性からの一視点をつけ加えようとするものである。
こうした姿勢は、効果の実証が世界的に強調されるこのエヴィデンス・ベイスト・メディシンの時代にあってとりわけ重要であろう。アルドリッジ(2003)は「エヴィデンス・ベイスト・メディシンはカウンター・バランスを必要とする。エヴィデンス・ベイスト・メディシンに対抗するというのではなく、そうした一つの考え方だけが[臨床]実践のための合法的視点であるという概念に対抗するのである。」と述べている(p.5)。
「介入と効果」にとどまらない音楽療法の位置づけに関連する概念としては、まずBruscia(2008, 原書1998) の示した「プロセスとしての健康」が挙げられよう。Brusicaは、健康とは個人の身体、心、魂のみならず、その取り巻く社会や文化を含むホリスティックなものであること、健康と不健康に二分されるものではなく絶えず変化する多次元的な連続体であること、そしてさらに動きを伴ったプロセスの中でのその人自身がどう存在するかという問題であることを定義づけている(p.90-91, 原書p.84) 。またAldridge(2003)は、「障碍の概念における関心の焦点は、生物学的欠損から患者の固有的経験へと移行してきた」とし、「音楽療法とは、多様な領域から持ち込まれた概念が凝集されたものであり、医療のような隔離された領域ではなく」、西洋医学ばかりでなく伝統的医療や心理療法、創造的芸術療法の新しい知を巻き込むものであると述べている (p.7)。Kenny (2006, 原書1989)は、療法のプロセスを「療法士とクライア〔エ〕ントの関係性に基盤を置く、親密な空間」において、両者が「ふたつのうつくしさ」として「出会う」と捉える。興味深いのは、その図が、対象者を中央に描いて療法士が介入するというかたちとは異なり、療法士とクライエントをふたつの同じ円として示されていることである(p.100-106, 原書p.75-82)。さらにStige (2008, 原書2002)は、音楽療法対象児の発達とは、対象者が環境に合わせて変わるだけでもなく、環境が対象者に合わせて変わるだけでもなく、双方が少しずつ変わることによって起きるという「相乗的相互作用の視点」を実例と共に示す。彼は療法を「関係において学ぶ事」と捉え、「文化化」という言葉を用いる (p.183-198, 原書p.135-148)。これらの概念からは、療法のプロセスを症状改善の右肩上がりの直線として見ることや、また療法士と対象者を介入する者とされる者という二元的な構造として見る枠組みからの緩やかな脱却がイメージされる。
こうしたことから、筆者は臨床の場で参加者たちが感じ取っている「意味深さの経験」に関心を抱いた。実際のセッションはそうした経験によって進行し継続しているからである。この研究は、ある症例の 6 年間136セッションにわたって、療法士が経験した意味深さについて探索しようとするものである。
取り上げる症例とその特徴
取り上げるケースのクライエントは、視覚障碍と重度知的障碍を持つダウン症女児で,表現言語は6年間を通して独自の単語が数語であった。身体障害はないが、介助なしで歩けたのは4年生のときであった。幼時から音楽に対しては際立って強い意志と受容/表現行為があり、自宅では電子キーボードで遊んだり、周囲の音楽に耳を傾けたりして過ごすことが多かった。今回取り上げる小学校6年間の間、一回40-60分の個人音楽療法に熱心に参加したが、療法士からの明白な目的を伴う直接的な療法介入を受け入れることには困難がつきまとった。
この症例を研究題材としてこれを用いる理由から述べたい。まず一般的な設定に視点を移し、私たちが非定型とされる人々と間近に接するときのことを考えてみたい。そうしたとき、私たちはしばしば、自分たち定型者を見るよりも深く、くっきりと、人間であるとはどういうことなのかを教えられることがある。同じように、音楽療法の対象者の中でも、即時的な効果が目に見えて上がる類の人たちではなく、効果が上がりにくかったり、問題が繰り返し回帰したり、表面的な健康状態は徐々に低下していくような人たちの中に、かえって音楽療法のひとつの本質が見えることがある。
この症例の特徴は、 重度知的障碍により言語コミュニケーションが極めて限られている、 生来の性向と視覚障碍により、音楽への強い関心と能動的関わりが顕著である、 療法士側からの介入計画の多くに対して躊躇が見られ、セッションの方向性が療法士のみならずクライエントによっても強くイニシアチブを取られている、という三点に要約することができる。その経過は複雑で、「クライエントへの治療的介入による即時的効果」のみを単位としては捉えきれない。一方で音楽の存在意義が非常に高く、クライエントの“すこやかさ” のためには音楽療法セッションをどうしても続けて行わなければならないという確信がクライエントを含む参加者全員の中に強く持続したケースである。冒頭で述べたような音楽療法という事象の「独自的な意味の広がり」を模索することに適したケースではないか
。
この研究における「意味深さ」とはどのようなものか
音楽療法臨床家は、「意味深い」経験について、「強い印象が残る」「(お互いに)はっとした」「言葉にできない意味があると感じた」「療法士の方が何かを受けとった」などということばで日常的に語るが、その中には、臨床的効果に直接関わるものも、そうでないものも含まれている。しかしいずれにしても多くは、論理的な依拠がない、他者を説得させられないなどとみなされ、研究議論としては扱われにくい。
「意味深さ」に関するもうひとつの難しさは、それが、個人的、文化的、歴史的コンテクストによって少しずつ違った側面を持つことである。この研究が扱う「意味深さ」を位置づけるため、AmirとStigeの概念を基盤として引きたい。
Amir (1992) は音楽療法の「意味深い瞬間(meaningful moment)」について、音楽療法士とクライエントへのインタビューを題材とした分析を試みている。Amirの「意味深い」という概念が本研究と共通するのは、「意味深い瞬間」が療法士とクライエントの間にあるいはそれぞれの中に起こる際立ったできごとであること、その経験が療法の進行に大きく関わるものであること、また、それは「感じられるもの」であって、測定したり明文化したりできない経験であるとしていることである。
しかしながら、異なる点もある。このAmirの研究(1992)では「意味深い瞬間」が療法のゴールそのもの、あるいはゴールに向けた起爆剤のようなものとして扱われていることである。それは、療法士の専門的能力及びそれを超える何かを駆使して起こされる異次元的で特殊な「瞬間」を指していると思われ、また「喜び」「うつくしさ」「変容」「本来の自分」「霊的な」「自由」といった人間主義心理学の価値体系を強く反映していると思われる(p.56-59)。
本研究は必ずしもそれらと対極に立つものではないが、本研究で扱おうとしている「意味深さの経験」は、もっと日常的な目線のものである。それはセッションの中で常時起きている小さな気づきの連鎖のようなものであり、療法の方向性を決め、継続していくための日々の糧でもある。何か目指すべき人間の在り方を先に決めてそこへクライエントを導こうとする「治療的」束縛をむしろ低めて、共に場を生きることからクライエントと療法士の間に生まれてくる「意味」を見つけ、深く経験することから方向性を生み出していこうという立場である。つまり、ここで言う「意味深さ」は、療法士によって付与されたり目指されたりするものではなく、互いの等身大の関係の中に生まれるものである。
Stigeは、Amir (2001) への「音楽療法の意味」をテーマとするインタビューの中で、「その意味を読むのは療法士とクライエントどちらの権限か」という質問をしている。さらに、「意味とは何か普遍的なものでそれを探すのが療法か、それともあらゆるものは、意味が創り出される可能性を秘めたものか」という問いも投げかけている(p.216)。ここには、従来の療法が、療法士の選びとる普遍的目標を前提とした一方通行のものであることへの異議と、Amirの概念も形を変えつつ結局は類似する路線をたどっている可能性への指摘が含まれていると思われる。
すでに述べたように、Stige (2002)は、「関係において学ぶこと、〔対象者と療法士を含む周囲の人々同士が〕文化化すること、自分自身と世界に関する文化的知識を蓄積する」という療法の定義を試みている(p.43)。この視点は意味の共構築という点で本研究に近い。ただし本研究は、個々の参加者に属する多次元的な意味の対峙には焦点を当てず、場に自然に形成されていった意味の集合的総意を象徴するものとしての療法士の経験に重点を置いている。この点については、本稿の最後でまた触れる。
以上をまとめると、この研究で言う「意味深い」経験とは、クライエントの「すこやかさ」をめざす設定の中で、療法士によって心に留められたできごとの解釈を指す。ただしそれは療法士個人に属する「意味深さ」にとどまらず、場に立ち上がる総合的意味深さを反映するものとして位置づける。そこでは、もちろん効果や発達も大きな位置を占めるが、それにとどまるものではない。また、いわゆるポジティブなことだけでなく、失望や想定外の印象、葛藤なども含まれる。
研究の目的と方法
この研究は、ある重度知的障碍児との長期にわたる音楽療法セッションにおける意味深さの経験について知識を得ることを目的とする。
題材として、症例研究 「音楽を身にまとった子ども〜自閉的傾向のあるダウン症知的障碍児との6年間〜」(生野、in press) の一部分として書かれた療法士のナラティブ・ストーリーが用いられる。このナラティブ・ストーリー作成までの手順の概観は以下のようなものである。
- 一次データ(136セッション各4-5ページの参与・直接観察の書き起こし記録とビデオ)の音楽経験形態によるカテゴリ−分け
- そこから表れる意味概念の同心円チャート化による関連づけ
- 意味概念を柱とした療法士のナラティブ・ストーリーの作成
この症例研究のナラティブ題材の内、療法士が「意味深い」経験と捉えている事柄を、類似するものに分類し、「価値側面」として名付けた。さらにそれら価値側面のサブカテゴリーを設けて、どのような経験であるのかを解釈した。
倫理的配慮
この症例の映像記録と書き起こし記録を残すこと、研究すること、研究を公表することについては、プライバシー保護を条件としてクライエントの両親の許諾を得ており、この研究内容についても承認を得ている。
「意味深い経験」を形づくる5つの価値側面
一般共有的価値
〜健常者側の社会的規範を軸として対象者を理解できること/理解できないこと、あるいは理解構造を変更することの意味深さ〜
6年間のナラティブ・ストーリーを、「意味深い経験」という視点から読み直すと、その最も皮相の部分に現れてくるのが、健常者側の一般的規範にのっとった価値である。それらは以下に分類される。
- 通じ合える部分を発見すること
- 〔クライエントを理解できずに療法士が〕異質感や疎外感を抱くこと
- 一般的基準によって一般的でないクライエントを理解すること
- 理解の体系自体が崩されること
考察
一般共有的価値は、障碍児を健常者社会の延長線上の「端」に位置するものと見る前提から生まれる。ここでいう健常者社会の代表はいうまでもなく療法士であり、クライエントを意識的・無意識的に療法士を中心に置いた健常者の社会へ包含しようとする視点を伴う。療法士に関する議論に含めるにはあまりにアマチュアと思われるかもしれないが、療法という設定にあっても自分自身の価値体系や人生観、理解の枠組みを完全に取り外すことのできる人はいない。よって、健常者側から見て「通じる」「わかる」ことが自然に意味深さを生じさせる反面、そこに不用意に療法士の内面のニーズが反映され、負の形での逆転移的視点を伴う危険もはらんでいる。
一方、本児のような重度知的障碍児の場合、専門的知識を持ってしても療法士が「理解できない」時間も非常に長い。こうした経験は、療法の場といえども療法士に異質感や疎外感を与え続けるが、それを「意味深さ」の経験の範疇から抜け落ちるままにするか、含めるかが、療法にとっての重要な分かれ道となるといえよう。後者の姿勢は、違和感を直視し、許容しながら抱き続けて新しい「意味深さ」への礎石にすることである。
この症例では、療法士に経験される率直な喜びと落胆の両方が糸口となって療法士をクライエントの世界に引き込み、療法士のクライエント観や療法観にさまざまな「修正」を起こし続けている。
発達的価値
〜クライエントの発達に関する意味深さ〜
障碍児の音楽療法において、発達の促進は中心的な柱である。しかし発達を目指す一般的な音楽療法の通念どおりには進まなかったこの症例では、発達というテーマの周囲で多様な意味深さの経験がされている。それらは以下のように分類される。
- このクライエントの発達の独特なアンバランスさに触れること
- 療法アプローチの直接的結果としての発達的伸長を認めること
- 発達的アプローチが作用しないどころか意識的に拒否されている印象を受けること
- このクライエントへの発達的アプローチの意味を再考すること
- 療法アプローチとの直接の関係は不明確なまま、発達的伸長を認めること
- 独自的な発達世界を発見すること
考察
障碍児の音楽療法の至上命題としての「発達」の位置づけは、この症例のセッション・プロセスに機動力や達成の喜びを生むと同時に、強い葛藤ももたらしている。しかしその葛藤の経験は療法を独自的な方向へ発展させるきっかけともなっている。
療法士は、こうした自らの多面的な意味経験を熟考し続けることで、このクライエントの独特の発達世界に関する仮説を築き、その中を生きるクライエントを支え、必要に応じて自身の発達世界観作り替えていくという役割に導かれていっている。このクライエントに限ったことではないかもしれないが、ひとりの人間が発達していくということは非常に包括的かつ個々に異なるプロセスであり、部分に分けて短い期間見るのでは捉えきれないことがある。とりわけ重度の知的障碍と高度な音楽感受性を併せ持っているこの症例では、水面下に有機的なからみ合いがあり、とくに発達的価値と自己内発的価値との独特な関係が、意味深さとして経験されている。
自己内発的価値
〜クライエントの内発的な音楽的欲求や満足に関する意味深さ〜
この症例において、クライエントがその障碍を突き抜けて強い個性や意志、いわば彼女らしさをありありと見せることに、療法士は常に注意を引かれ、意味深いと経験されている。音楽に関するクライエントの内発的な欲求はとても強く、宙を見つめる、忘我的表情になる、演奏に全身で取組む、部屋の出口に向かっていく(これについてはさまざまな解釈が可能である)などの行為から、内面が深く揺さぶられていることが示されている。自己内発的価値の経験は以下のように分類された。
- このクライエントの内発的自己の強さと真剣さに圧倒されること
- その性質を追跡し、解釈しようとすること
- クライエントの内発的欲求によって作られる空間ダイナミズムに巻き込まれ ること
- セッションのイニシアチブをクライエントの自己内発的方向性に譲ること
- 自己内発的行為の首尾一貫性を見出すこと
- 自己内発的目標のためのリソースの統合という成熟の瞬間に立ち会うこと
- 内面に拡大しつつある独自世界を垣間見ること
解釈
まず何よりも、このクライエントの自己内発的価値の強さが、圧倒的な意味として経験されている。そしてそれが強く経験されるとき、クライエントを「対象」として切り離す療法士の姿勢が切り崩され、クライエントにイニシアチブを譲ったり、自分自身の感情を解き放たれたり、療法士としての根本的な立ち位置を揺るがされたりしていく。クライエントに起きていることは、療法士にとって自分を含めた人間全体を祝福するような事柄になってきており、セッションにおける意味深さは、この自己内発的価値を境として徐々に、「療法士とクライエント」という縛りを脱していく。このクライエントとの療法における自己内発的価値は、多分に交流的な性質を持っていると言えよう。
一方で、クライエントの自己内発的世界の全容は外から見渡すことはできないものの、療法士の介入を拒むほどに閉じられた構造として自己完結していること、そしてクライエントの生物学的・認知的成長と共に成熟/開花していっているらしいこともまた意味として経験されている。
自己内発的価値は、初期にはたくさんの断片的なものとして経験されているに過ぎない。しかし4年目ごろを境に、クライエントは一貫性のある自己内発的世界で外に働きかけるようになる。例えば84回目のセッションで、クライエントはショパンの「雨だれ」前奏曲のベース音に合わせてビートを打ちたいという自分の自己内発的な音楽目標を意識し、以下のような多次元的なリソースを統合し始めている。
- 情緒的/認知的リソース:願望が自分の内側にわき上がるのを知的・感情的に受け止め、対処し始めること
- 情緒的/社会的リソース:うまくできない自分の在り方を他者(療法士とアシスタントと母親)との場で受け入れ、自分の目標を分かち合おうとし、積極的に助けを借りていること
- 知覚的/認知的/心理運動的リソース:聴くこと、見ること、模倣すること、様々な手の動きを試すことなど、持てる限りの能力を協応的に使っていること
- 包括的/保続的リソース:断念してもまた自分で持ち直し、意味のつながった努力を継続すること
このプロセスは、療法士に非常に意味深い経験として受けとられ、発達的価値と自己内発的価値の関連性の洞察に大きな影響をもたらしている。すなわち、閉じられたようにも見える自己完結的世界にはこのクライエントにとっての首尾一貫性が脈づいており、それをまるごと実際の音楽行為として実現することで、はじめて「内と外のリソースに開く」という大きな発達的成長を見せているのではないかという意味の発見である。それはいわゆる発達的音楽療法において一般的な、「動機づけ」や「正の強化子」といった断片的な音楽の使い方とは性質を異にするものとして経験されている。それに伴い、常に成長していっているクライエントの内的世界をさらに知ることが意味深い作業として意識されている。
対話的価値
〜場における言語的・非言語的対話に関する意味深さ〜
小さく親密な音楽療法室に6年にわたって定期的に集まってきていた4人は、お互いの物理的・心理的な特性を感じとりながら、さまざまなかたちの対話を交わしている。それは相互的場を形成する。そうした場における対話的価値は以下に大別される。
クライエントからの発信に関するもの
- クライエントからの発信を受け取ること〜支配的な質から共感的な質へ〜
- クライエントの音楽にまつわる行為すべてを発信として受け取ること
療法士からの発信に関するもの
- 療法士が音楽を発信し、その受けとられ方を解釈し、調整すること
やりとりに関するもの
- 音楽的な質に限定された音楽やりとりを経験すること
- 人格的な質が含まれた音楽やりとりを経験すること
- 音楽が人格的やりとりの背景に退いたと感じること
- やりとりで背を向けられると感じること
場に関するもの
- クライエントが場に開いていると感じること
- クライエントが場を回していると感じること
- 場があたたまっていると感じること
- 新しい場への信頼感が生まれ、参加者のひとりとなること
- 場がいつも育っていっていると感じること
解釈
初期、対話的価値は、療法士・クライエント各々からの発信や、二者間のやりとりの成立といった点に主に意味が見出されている。コミュニケーション能力が未発達なクライエントも、こと音楽に関しては、強いメッセージを発し、療法士にとってその音楽行為すべて(音、声、楽器選択と使い方、視線、表情、姿勢、動きなど)がクライエントからのコミュニケーションとしての意味を持っている。また、療法士の言語にはほとんど反応しないクライエントも音楽であれば積極的に受けとるため、療法士は音楽を発信してはその受けとられ方を見て、調整する。それはクライエントと代替的対話を構成していっている。こうした互いからの発信が積み重なり、やりとりの原型と呼べるものが音楽の中ではゆっくりと育っていっていること、また当初は音楽だけが行き来し、人格は取り残されるという状態が続いたが、長い時間をかけて人格を、さらに共感を前面に出したものに変化していっていることに意味が見出されている。
しかしクライエントは年齢的成長とともに自閉傾向も強めていくというジレンマが訪れ、4年目ごろからやりとりはかえって困難さを伴うようになった。そのときに今度はクライエントの方から示されるかたちで浮上してきた新しい対話のかたちが「場」であったと言えよう。
この「場」とは、上述のような特定できる発信ややりとりと並行するかたちで、症例の最初から少しずつ醸成されていたと考えられる。そもそも、自己内発的価値が突出し、一般共有的価値においても発達的価値においてもわかりやすい展開をしなかったこの症例において、場の参加者4人(療法士、クライエント、アシスタント、母親)は、「この子どもはどの道筋を通って、どの方向へ育っていくのか、どのようなアプローチがそれを支えることになるのか」を常に問い続けていた。クライエントの内面は言葉としては表されないが、彼女自身も音楽にすがりつきながら懸命に成長を模索していた。言い換えれば、4人の間には共通した問い「どこへ、どうやって」があり、思考、感情、言葉(あるいは前言語的コミュニケーション)、音楽、動きが常に行き交い、四方向からの緊迫した、進行形のコミットメントがあった。そしてそのコミットメントの4年近くにわたる平衡状態が、対話の場=コミュニティを形成していったのである。
自閉的行動が強まった新しい段階に話を戻すと、ほぼ1年が経過した5年目ごろから、クライエントの場における相互依存的な存在感が増したことを療法士は経験している。言い換えるなら、ふたりの直接的コミュニケーションが行きづまったとき、クライエントが自然に代わりの方法を選ぶかのように「相互的な場」を使い始めたと感じたのである。クライエントは場の人物や物の特性や役割を的確に捉え、それらを自分のいきたい方向性のために配置したり動かしたりしている。それはもちろん自閉的・操作的な特質も示してはいたが、その上に照れや喜びといった相互人格的な感情表現の「温度」があり、「場」は参加者にたちとってコミュニケーションの重要な媒体となったことが感じられた。療法士がこの行為の持つ意味に気づき、受け入れ、参加することで場はあたたまり、さらに育っていった。
この展開は、療法という事象自体も、療法士とクライエントの相互依存的なプロセスであることを示している。
共生的価値
〜クライエントと療法士の対置関係の変容に関する意味深さ〜
この「相互依存的」という関係は、「障碍者対援助者」という従来の役割と距離にとらわれた見方だけではもはや説明がつかず、新しい対置関係が必要となる。ただしそれは、療法士やクライエントの役割を放棄したり離脱するということではない。人間同士としての根本的な尊重や問いを通じて双方が出会い直し、伝統的な役割関係が再編されると言えよう。もちろん、音楽療法士は皆、クライエントへの尊重や問いに立ってその臨床セッションを行なっているであろう。しかし「共生的対置」の中では、療法士はクライエントをさらに対等な、いわば異なる装備を背負って同じ旅を歩く「人間同士」として見ることになる。このケースで経験されている共生的価値は以下のように分類される。
- 畏敬の視線
- 違和感と見送り
- クライエントの経験をわがことに引きつけて感じること
- まるごとの一貫性を持ったクライエント世界の尊重
- クライエントの見えない世界を伝える媒体としての音楽
- ふたりの人間としての多様な居方の発見
- 二者の間をつなぐ媒体である「人間としての普遍的苦しさ」への開眼
- このクライエントの療法士としての居方が育てられること
- 療法士の療法観全般が育てられること
解釈
共生的価値は、見方によっては職業的立場の逸脱とも解釈できるため、保健サービスとしての音楽療法の論議では通常枠外に置かれるか、論ずることをタブー視される傾向にある。一般に「療法の中で起こる変化」に関する学問的・専門職的議論は、クライエントの変化に集中する。療法の第一義的目的はクライエントの健康の改善だからである。その際、療法士の側にも当然起こる変化についての言及は、確信の欠如やアマチュアリズムの象徴とみなされることさえある。この傾向は西洋的医科学の文化に根ざすものかもしれない。しかし、本症例では、臨床を続けていくにあたってこの価値が療法士及び療法の場に与えた影響は大きく、意味の体験として除外することはできない。
例えばこのクライエントが音楽の中でもがき、何かを成し遂げたり成し遂げられなかったりする姿は、療法士の中に畏敬の感覚を生んでいる。なぜなら、このクライエントにとって音楽は単なる楽しみではなく、人生の重大事であることに気づいたからである。そしてそれは「障碍者であろうと子どもであろうと、一人ひとりの人間が自分の大きな宇宙を抱えて自分なりの道を歩いている」という洞察を療法士にもたらしている。
逆に、すれ違いや期待はずれも引き続き経験されている。しかし一般共有的価値では埋めなければならない違和感として感じられたすれ違いが、ここでは「見送る」という意味となって経験されている。
また、畏敬にせよ違和感にせよ、療法士はクライエントの内的経験の「内容」を理解しようとするのではなく、「それに伴って起きているであろう感情」を我がことに引きつけて想像し追体験する様子が見られる。
さらに、療法士はクライエントの障碍を健常状態に付け加えられたり差し引かれたりしたものとして見るのではなく、それも含めてのひとつの完成した世界として見るようになっている。例えば、クライエントのその時々の自閉的引きこもりは、彼女が自分の世界を生きるために行うことが必要な手順であり、その上に自分の成長を築いていくものとして捉え直されている。
そして音楽が象徴的媒体となって、こうした繊細で刻々と変わるクライエントの内的世界を伝えていることにも意味を見出している。
このような療法士の視線の変化は、必然的にふたりの対置関係にも多様な質をもたらし始める。例えば、「音楽共同者」「試合をしているようなふたり」「療法士がクライエントの外側ではなく内側から歌いかける」といった経験が記述されている。中でも最も大きい変化は、療法士がクライエントの中に「障碍者としての」ではなく「人としての」苦しさを見つけ、共感していることである。この気づきは、他の何よりも、療法士に「共生している人間同士」という感覚を呼び起こしている。療法士のナラティブ・ストーリーの中には以下のように記述されている。
ここでいう「生きることの苦しさ」は、障碍児だから負っているといった性質のものではなく、人間が普遍的に持っている生きるもがきのようなものである。よって、療法士もクライエントの苦しさを肩代わりしたり軽減したりする立場にはなく、この「苦しさ」をはさんで、対等に向き合うこととなった。こうした療法において、「苦しさ」は切除するべき病巣ではなく成長の芽吹く場所であり、療法士は「懸命に傍らに居ること」と「うつくしさを創りだすこと」で、そこに参加する存在となる。
こうした共生の意味経験は、療法士とクライエントを伝統的な対置関係から解放することによって可能になっているが、翻ってこれがこのクライエントの療法士としての役割に新しいインスピレーションをもたらしたり、療法全般についての新しい洞察につながったりもしている。
パブリチェビック(2002, 原書1997)は、治療関係というものが、治療者・患者双方の抑圧された心理的欲求から、健康で強い役割の治療者と、その援助に受動的に依存する患者というアプローチに陥りがちであることを指摘し、そうではない「同伴者」としての治療者の在り方を示唆している(p.266-268)。この症例では、対話的価値によって育てられた相互的場が共生的価値を生む基盤となったと言えよう。
結論
5つの価値側面の位置関係に関する考察
臨床プロセスの「意味深さ」を構成する多層的な価値は、ポリフォニーのテーマのように繰り返しながら、複雑に関係し合って動いている。この「意味深さ」の経験によって、セッションは生きているものとして続行していく。その全体的概観は図1のように考察される。
一回一回のセッションにおいて一般共有的価値、発達的価値、自己内発的価値は具体的な「よすが」や「枕木」のようなものとなって、クライエントを中心とした活発な共時的空間を作り、また一瞬先の方向性を編み出している。これら三つの価値を巡る模索は、回数を重ねて参加者の間に対話的価値を育てる。対話的価値の果実は、毎回のセッションに返されていくと同時に、通時的にはひとつの臨床的物語を編んでいく。この物語に参加することで、参加者の個人的な生にも共生的価値が、にじむように影響を与えていく。それは、臨床に対する取り組みにも作用していくと同時に、臨床を離れた私的な領域の世界観にもなんらかの変化をもたらす。つまり、ひいては一般共有的価値の修正につながる兆しも含んでいることになる。
場に立ち上がる意味
さて本研究では、一貫して「療法士に経験されている意味深さ」を題材としたが、この「意味深さ」が療法士個人に帰属するものという考えにはない。クライエントとのやりとりにおいて療法士に経験されている「意味深さ」とは、療法士とクライエント両者の関係に属するものであり、それを療法士の目という装置を通して見ていると考える。これは客観的正確さを立証するための方法ではなく、プロセスに参加している療法士を通して解釈されるひとつの一貫した真実を認識するための方法である。
その意味では、そこには母親やアシスタントの視点も入り込んでいる。セッションをしていくにあたり、4人の感じる意味深さは言語的にも非言語的にも強く影響し合っているからである。「意味深さ」は4人の真ん中に現れているとも言えよう。
とくに対話的価値の「場」の概念や、共生的価値において、セッションにおける意味深さは徐々に療法士-クライエントという縛りを脱し、集合的になっていくことが洞察されている。これは、冒頭で引用したStige(2008, 原書2002)の概念「関係において学び合うこと」や「文化化すること」といった、個と個が際立つ形での相互関係とは幾分異なる。
この集合性には、あるいは言語による自己表明が難しい重度知的障碍児という本症例の特性も関連していようが、それだけではなく、文化的特性が背景の一部を担っているとも考えられる。日本人は、「個のアイデンティティを超えて集い」、「言葉を介さずに場の意味を共有する」(生野、2005)独特のコミュニティ文化を生活のあらゆる場面に応用しており、心身の健康の領域もまた例外ではないからである。しかしながらこの文化的問題については、本稿では可能性を示唆するにとどめる。
直線的・原因結果的視点と円環的・相互的視点
昨今、音楽療法はじめ福祉、教育といった関連領域にも強い影響を及ぼしているエヴィデンス・ベイスト・メディシンは、介入と結果を明確にすることを求める。この視点を煮詰めていくと、介入する側は定点に立ち、目標を掲げ、介入される側に変化を起こすという手続き構造に集約される。西洋を起点とする近代音楽療法の実践や研究の多くは、医科学的なものはもちろん、行動主義的なものから人間主義的なものに至るまで、多かれ少なかれこの前提の影響を受けているように見える。前述のAmirやStigeもその例外とは言い切れない。
本症例の中ではしかし、「相互的な場が育つことにおいて、療法士とクライエント双方の変容が醸成されていく」という療法の性質が顕現化してきた。これは「ある個が別の個を助ける」という直線的な療法の視点とは何か質の異なる、円環的、あるいは相互的に影響を受ける療法のひとつの視点と言えよう。
ここでもう一度、本稿は介入—効果の療法プロセスを否定するものではなく、違った方向からカウンター・バランスとしての見方を示唆していることを述べておきたい。また、これは、療法が方向性のないレクリエーションや偶発的・実験的芸術催事であってよいということも意図していない。療法とは常にクライエントのすこやかさを第一義として構成される場である。しかし本研究からは、療法的方向性をもって意図的に構成された場であろうとも、人と人が場を介して相対するということはすなわち相互性をもたらすという見方、そして音楽を通して関わり合えば、療法士といえども定点に立って出来事の成り行きをすべて操作することはほぼできないという見方が示唆されている。
むしろ療法士が自ら相互影響の中に身を投じることによって定点に立たないという位置づけも、療法の根幹的視点のひとつとして仮定できる。こうした音楽療法の性質は、一定の数の音楽療法士によって堂々とあるいは躊躇しながら日々の実践に取り入れられていると思われる。療法におけるそうした経験を単なる惰性的習慣に陥らせることなく性格づけするために、参加者による意味の経験の分類と解釈を通して理解の一つの方法を模索したのが本稿である。
「意味深さ」を構成する価値側面の研究への展望
臨床の「意味深さ」を構成する多層的な価値側面を視野に入れて、入念かつ理論的に理解するためには、ひとつの症例に多角的な方法論を使うことも必要になると考える。例えば言語によるインタビューを伴う・伴わない形の解釈学的・現象学的研究や、創意的な音楽分析、エスノグラフィ研究、ナラティブ研究などが有用であろう。
本研究は今後、上記のような方法を視野に入れ、相互的場の関係に焦点を当てて進めたい。
参考文献
Aldridge, D. (2003). Staying close to practice: Which evidence, for whom, by whom. Music Therapy Today, 4(5). http://www.wfmt.info/Musictherapyworld/modules/mmmagazine/magazine_start.html
Amir, D. (1992). Awakening and expanding the self: Meaningful moments in music therapy process as experienced and described by music therapists and music therapy clients. New York: Unpublished Doctoral Dissertation, New York University. http://steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/jts390/Dissertations/AmirDorit1992.pdf
Bruscia, K. (1998). Defining music therapy. NH: Barcelona Publishers. (生野里花訳. 音楽療法を定義する. 東海大学出版会. 2008.)
Ikuno, R. (2005). Development and prospect of music therapy in Japan(生野里花. 日本における音楽療法の展望). Voices: A World Forum for Music Therapy, 5(1). https://normt.uib.no/index.php/voices/article/view/211/155
Ikuno, R. (in press). Ongaku o Mi ni Matotta Kodomo ~Jiheitekikeiko no Aru Daunshochitekishogaiji tono Rokunenkan ~. In. Sakaue, M.(Ed.), Ongaku Ryouhou Shoreishu (tentative title). Tokyo: Iwasaki Academic Publisher. (生野里花. 音楽を身にまとった子ども〜自閉的傾向のあるダウン症知的障碍児との6年間~.阪上正巳編. 音楽療法症例集[仮題]. 岩崎学術出版.)
Kenny, C. (1989). The field of play: A guide for the theory and practice of music therapy. Ridgeview Publishing Company (近藤里美訳. フィールド・オブ・プレイ. 春秋社. 2006.)
Pavlicevic, M. (1997). Music therapy in context: Music, meaning and relationship. Jessica Kingsley Publishers (佐治順子訳. 音楽療法の意味-心のかけ橋としての音楽. 本の森. 2002.)
Stige, B. (2001). Layers of meaning. Nordic Journal of Music Therapy, 10(2), 209-220.
Stige, B. (2002). Culture-centered music therapy. NH: Barcelona Publishers.(阪上正巳監訳. 文化中心音楽療法. 音楽之友社.2008.)