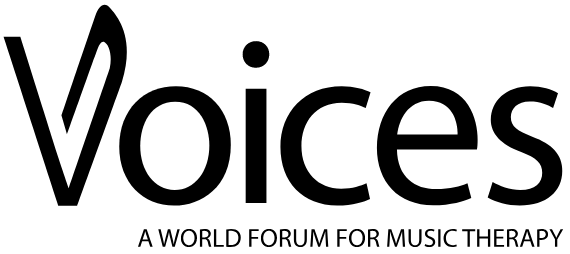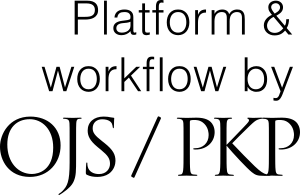[Special Issue on Music Therapy and Disability Studies]
障害のある人の表現に関する生政治的視点:音楽療法の事例から
三宅博子
はじめに
近年急速に発展しつつある、障害学の学際的な研究分野では、「障害」は医学的な病理としてではなく、社会文化的に構築されるものとして理解される。これは、ポジティブな政治的・文化的アイデンティティーとして“障害を主張する” (Linton 1998)という視点から、障害/健常、正常/異常、ジェンダー、人種、エスニシティなどといった、人々を分割する境界線を揺さぶろうとする政治的な企図を含む。しかし、音楽療法の領域では、障害学の考えはほとんど省みられてこなかった。なぜなら、音楽療法はこれまで、社会文化モデルや政治モデルよりも、医学モデルに依拠してきたからだ。本論では、近年の障害学の知見を参照して、音楽療法に内在する権力関係の問題について論じる。
音楽療法に内在する権力関係
近年「障害」という概念は、科学や医療の分野だけでなく、人文科学・社会科学の分野の研究主題になっている。発展しつつある障害学の分野では、障害の社会文化的構築に焦点を当て、生物学的視点から文化的視点へと障害に対する認識を移すことによって、障害の社会文化的分析を行っている(Straus 2011: 4)。しかし、音楽療法は伝統的に、医学モデルと強く結び付いてきた。音楽療法士は、しばしば臨床的な設定で、クライエント個人とその病理に焦点を当てて取り組んできた。このような状況では、セラピストはクライエントとの関係構築において、専門家としての地位に内在する権力に依存してしまうことがありえる。コミュニティ音楽療法は、そのような権力関係から逃れようとするアプローチの一つであり(Stige & Aarø 2012)、音楽療法士の中には、非‐抑圧的な実践の発展へ向けて歩み始めている者もいる(Baines 2013)。コミュニティ音楽療法を支える理論は、障害の社会文化モデルとも合致する。
しかし、音楽療法の分野をより社会へと開いていくためには、コミュニティ音楽療法が、単に音楽活動を臨床的な設定(閉ざされた音楽療法室)から、コミュニティの設定(地域に開かれた場)へ移そうと試みるだけでは不十分である。なぜなら、単に障害のある人の社会参加を促進するだけでは、健常/障害、健康/病、正常/異常、マジョリティ/マイノリティといった、人々を分け隔てる二項対立的な境界線は変わらないからだ。これらの境界は、固定的実体として社会のどこかに存在するのではない。そうではなくて、私たちの内に価値観として内在化されていると同時に、たとえばクライエントとセラピストのような、人々の相互関係を通して遂行(パフォーム)される。スーザン・ハドレイが指摘するように、音楽療法士である私たちは、西欧中心主義、異性愛主義、資本主義、精神医学、心理学、医療などの、支配/従属のナラティヴによって形作られる社会に生きており、クライエントを「どのように見、どのように聴くか」という基本的枠組みも、そのようなナラティヴによって形成される(Hadley 2013)。つまり、日々の音楽療法セッションにおける私たち自身の行動が、上に挙げたような境界線を支え、不平等な権力関係を維持する危険があるのだ。この問題と取り組むには、これらの境界線が社会でどのように形作られ、音楽療法の場においてどのように表れてくるのかを吟味しておく必要がある。
音楽療法と生政治
本節では、フランスの哲学者ミシェル・フーコーによる生政治の概念(Foucault 1990)と関連づけながら、音楽療法の場で働く権力関係のメカニズムについて論じる。
フーコーによれば、生権力とは、生の全ての側面に影響を及ぼす、近代の統治の一形態である。生権力は、身体の規律権力と、人口を管理する生政治という、二つの軸によって発展してきた。前者は、人間の身体に照準を当てており、個人に内在化されて、規律にふさわしくふるまう“従順な身体”を作り上げる。後者は、生物学的な種としてのヒトを焦点とし、出生率、死亡率、生殖や疾病などに介入して、人々を管理調整する。生権力とは、これら二つの権力を組み合わせ、人間を個人として、かつ集団として管理する技術である。
生権力の機能は「正常化」である。すなわち、そうあるべき規準としての“正常”を設定し、規準に従って人々を振り分け、社会のなかへ配分することだ。“健康”の概念を例にとると、まず医学的データや住民調査などの統計に基づいて“健康”の規準が定められる。次に、“規準”との差異の度合いによって“疾病”や“障害”が同定され、“患者”、“障害者”、“犯罪をおかす危険人物”といった位置づけが割り当てられていく。そして、規準を“逸脱した”身体は、治療やリハビリテーション、時には拘禁などによって“よりよい”方向へ向かうよう働きかけられる。生権力は、家庭、学校、会社、病院、といった様々な形で社会に配置されている。生権力の体制は、生物医学的知識や人々の社会的相互作用、社会の文化社会的・経済的・政治的構造などが密接に絡みあって形作られている。
では、音楽療法の場において、生権力として働く音楽的‐療法的規範とは、一体どのようなものだろうか。それは、音楽療法における“音楽的コミュニケーション”の概念と関わるものと思われる。近代音楽療法では、音楽の持つコミュニケーション的性質に、療法的意味や人間存在の本質を見出そうとする見方が一般的である。もちろん、筆者はここで、音楽療法でクライエントと関係を築くことの重要性を否定しているわけではない。だが、筆者はここに、音楽行為を通じてある種のコミュニケーションのあり方を強いる「コミュニケーション=音楽」の体制という問題がひそんでいるのではないかと考える。このことについて、音楽療法における音楽的相互作用の生物学的根拠として引用されることの多い、コミュニケーション的音楽性 (Malloch & Trevarthen 2009)の概念を参照して、さらに考えてみたい。
コミュニケーション的音楽性の考えでは、赤ちゃんと養育者とのコミュニケーションにおいて、発話のタイミングやテンポ、声色、身振りなどのパターンに顕著な一致が見られる。視覚・聴覚・触覚を介したマルチモーダルなやりとりが両者の間でリズミカルに繰り返されるにつれて、ひとつのメロディのような“流れ”が形作られ、感情的な質や起承転結を持つ“音楽的”ナラティヴとして共有される。このような「原会話」の音楽的特性は、私たちが他者と意味を共有するのに必要な、人間の生得的な能力に基づくものとされる。
しかし、この理論を音楽的コミュニケーションにおける“規範”として、たとえば自閉症のクライエントの音楽表現の解釈に当てはめてしまうとしたら、どうなるだろうか。ここでの音楽療法的介入は、“西洋社会における言語コミュニケーションのモデルに依拠した、“正常な”コミュニケーションの様式が、暗に想定されているように思われる。そこでは、共有すべき音楽的構造はあらかじめ音楽療法士によって設定され、クライエントはそれに“合わせる”ことが求められている。これは、“正常”なコミュニケーションの様式を設定し、クライエントの音楽的表現の“逸脱”の度合いを測り、クライエントを“あるべき姿”へと方向づけていくという一連の手続きによって、クライエントの生を操作する様式だということも出来るだろう。この操作には、人間のコミュニケーション能力の生物学的根拠としてのコミュニケーション的音楽性、社会的相互作用や言語的・非言語的コミュニケーションの障害としての「自閉症」という診断、音楽のドミナント―トニック構造や情動的な質といった機能づけなど、様々な領域における(仮説的)前提が組み合わせられている。じっさい、これらの前提は自閉症者のみに影響を与えているのではない。精神障害者、発達障害者、認知症者、昏睡状態の患者といった、私たちが出会うクライエントの多くが、“正常な”コミュニケーションに困難を抱えている人々と見なされてしまうのだ。
障害のある人々の音楽表現に対する文化的視点
クライエントの音楽表現は、コミュニティにおいてどのように受け止められ、尊重され、共有されるべきなのだろうか?筆者は、他の多文化的な出会いと同じように、クライエントの音楽表現を、その世界観や他者との関わり方が織り合わさったものとして捉えられるべきだと考える。ふたたび自閉症を例にとると、多くの自閉症者が、文化的・音楽的表現を含む独自の存在様式を持っていることを認めるよう提唱している(Headlam 2006)。この視点からクライエントの音楽表現を理解するためには、障害のある人の経験に関する現象学的研究、障害のある人によって書かれた手記、障害学の近年の知見などが参考になる。
今年の夏、最初に蝉のジージーという鳴き声を聞いた時も、僕は耳慣れない音に驚きました。だからといって、それが何の音で、どこから聞こえてくるのか考えないのです。ただ、引きつけられるように耳をすますと、音がこだまするように僕の脳に響きます。僕は何もかも忘れ、鳴き声を聞くことだけに集中するのです。こんな時、口で表せないくらいの幸せを感じます。まるで、自分がこの鳴き声を出しているかのような錯覚に陥るからです。人とうまくコミュニケーションできない僕にとって、他の生き物と共鳴できるこのひとときは、地球の一員として生きている実感を得ることができる貴重な時間なのです(東田2012:132-133)。
異文化、あるいは異なる生の様式との出会い
これらの視点から考えられるべきことは、異なる文化や音楽性を持つクライエントとセラピストが、どのようにして協働し、共有の時空間を一緒に創り出していけるのか、という問いである。村上は、定型発達者(Neurologically Typical)が、言語や人間関係といったような事物に与えられた文化的意味をいったん括弧( )に入れることによって、そのような経験に到ることができると述べている。そこで、いかにしてそのような経験に到るのかの手掛かりを得るために、日本の作曲家・野村誠が自身のコラボレーション的な音楽実践について書いたエッセイから、あるエピソードを紹介したい。それは、インドネシアのポンジョン地方の山中で、音楽的背景の異なる3人の音楽家と即興演奏をした経験のエピソードである。
鍵盤ハーモニカを持って即興演奏に加わったぼくは、最初、大いに戸惑った。鍵盤ハーモニカは西洋音楽の12平均律に調律されている。ところが、他の奏者の楽器は、ジャワとタイの音階に調律されている。ぼくには、3つの異なる音階が共存する中で、どの音を吹いても、何か馴染めないような気がして、模索の連続だった。でも、音楽は「音を全感覚で体感する行為」なのだから、音律については考えないようにして、ただ、全身で音を感じようとした。
日本とは全く違う鳴き方で、ジーワンジーワンと蝉が鳴いている。心地よい風が吹き、木々がざわめいている。ぼくは、アナンやスボウォ(共演者たちの名前)と演奏しているだけではない。蝉とも、風とも、この場にある全てのものと共演している。・・・音に名前をつけることをやめて、全ての音にニュートラルに向かう。そこには、音がある。色んな音が鳴り響いている。それに、何かを感じて、自らも音を発したい衝動に駆られる。そして、音を発する。ただそれだけだ。
>
ぼくは、徐々に自分の概念化された耳から解放されて、音律などについて気にせずに鍵盤ハーモニカを演奏できるようになっていった。鍵盤ハーモニカだけではなく、風、葉っぱ、石、田んぼ、用水路の水、あらゆるものと対話を交わし続けた(野村2009)。
このエピソードから示唆されるのは、私たちがあらかじめ与えられた文化的意味を括弧に入れて、他者の経験の主観的な現実を共に経験するために必要な、次の三つの局面である。すなわち、異なる生の様式と出会うこと、異なる生の様式を感じとること、異なる生の様式をつなぐこと。次節では、筆者による音楽療法実践事例を、この三つの視点から記述する。
他者の生と出会う:2つの事例から
しょうた
しょうたは、重度の重複障害(視覚障害、知的障害、身体障害)のある、13歳の少年である。彼は人と関わることが大好きだったが、障害のために、遊びやコミュニケーションのスキルを発達させる機会が限られていた。彼は5歳の時に音楽療法を開始した。筆者が音楽療法士として出会ったのは、彼が12歳の時だった。
筆者がしょうたと出会った時、彼は“いや!”、“おしまい”、“やらない”といった否定的な言葉をよく発していた。はじめ筆者には彼の意図が見えず、単なる拒否のサインだと思っていた。ほどなくして、これらの言葉が場面にかかわらず衝動的・習慣的に出てくるのではないかと感じるようになった。ある日、しょうたが“いや”と言ったとき、コ・セラピストはすぐさま“いや”の歌を即興的に歌った。するとしょうたは、大笑いしながら“いや”と繰り返した。それは、“いや”という言葉が、彼自身の表現として真摯に受け止められた最初の瞬間だったのだ。それから筆者たちは、しょうたが“いや”という言葉で表現する、豊かな内的世界に気づくようになった。しょうたの世界では、“いや”は、“関わって!”、“ぼくの言うことを聴いて”、“こわいよ、音をやめて、何か他の曲を弾いて”、“おいていかないで、もっとゆっくり弾いて”、“ああ、よかった。さあ、次の活動へ行こう”、“変なの!面白い~”、“大好き”、などを意味している。
異なる生の様式を感じ取る:しょうたのピアノの世界
しょうたの“いや”の世界を分かってくるにつれて、筆者は、彼独自のピアノ演奏スタイルに気づくようになった。しょうたは、左手を使って、鍵盤の低音部から高音部へ向けてグリッサンドをし、そして低音部へとグリッサンドで戻る。筆者は、この低音部から高音部へ上行し、低音部へと戻るという一連の流れを、彼にとっての「一曲」、すなわち演奏の基本構造と解釈した。そして、このピアノ曲を協働で創っていくのだと仮定して、彼の演奏に加わることにした。音の落書きをし合うような短い即興的やりとりの後、彼は低音へとグリッサンドし、満足そうに“おしまい”と言った。
この事例において、しょうたの演奏の基本構造は、彼の視覚障害から生じてきたものではないかと考えられる。というのも、視覚に障害のある彼は、ピアノの全体像を一目で把握することが出来ない。彼にとっての「ピアノ」は、鍵盤の“手触り”、聴こえてくる“音”の違い、手の届く限りの“幅”として感じとられるのではないかと思われる。彼のピアノ演奏は、ピアノから与えられる(affordance)彼自身の身体感覚の表現である。それは、しょうたのピアノの世界として捉えられるだろう。この場面において、彼の視覚障害は“ハンディキャップ”としてではなく、彼の音楽表現のリソース(資源)として活用されている。しょうたとの音楽的相互作用を通して、筆者は徐々に、彼がどのように状況を感じ、世界を認識しているか、また同様に筆者自身がどのように状況や世界を認識しているかを、感じ取るようになった。
異なる生の様式をつなぐ:バンド演奏
最近しょうたは、“Hello”、“How are you?”、“I love you”など、英語のフレーズを流暢に発するようになった。そこで筆者たちは、英語で即興的に歌う活動を始めた。この活動は、バンドで演奏するのに必要な技術を発展させる助けとなった。彼はリードボーカルとして表現力豊かな声を聴かせ、筆者たちセラピストは、ギターとピアノを担当した。時には彼の祖父も、打楽器で加わった。しょうたの歌手としての能力は、家族や学校の先生に認められるようになった。彼の母親は、彼女の好きなポップソングをしょうたと一緒に歌い、時には一緒にカラオケに行った。また、彼は学校の文化祭で、スティービー・ワンダーの曲“I Just Called to Say I Love You”を、メインボーカリストとして歌った。このように、彼は歌うことによって、他者との新たなつながりやコミュニケーションのあり方を創出している。
なおや
なおやは11歳の時に、副腎白質ジストロフィー1 と診断された。病が急速に進行するにつれて、彼は通常の意味でのコミュニケーションをとることが困難になっていった。現在、彼は植物状態に近い状態にあり、外界からの刺激に反応がないとされている。しかし筆者は、彼の呼吸、覚醒レベル、筋緊張の状態、口の動き、まばたきといった、身体の微細な動きを彼の表現と捉え、彼や彼の家族と共に、音楽作りを試みてきた。
異なる生の様式と出会う:鳥笛の響き
初期のセッションで、なおやはピアノの鍵盤を乱暴に叩き続けた。筆者は、何か構造的な活動を導入したいと思っていた。ある日、ピアノを演奏している時に、彼の叩くリズムに合わせて筆者が体操のような動きを始めると、なおやは筆者の動きに従って動き始めた。その様子を見て、筆者はこの活動を発展させることが出来るのではないかと考えた。しかし、活動が一段落したところで、不意になおやは筆者に向かって鳥笛を吹き鳴らした。その音が思いがけず鋭いものに感じられ、筆者はたじろいだ。
なおやの吹いた鳥笛の響きは、筆者が音楽療法に関する自身の暗黙の前提に従わせようとしていたことを気付かせた。筆者には、無意識のうちにクライエントの表現を、筆者の側の見方から“音楽的に”あるいは“療法的に”“発展”させていこうとする意図があった。筆者の解釈では、なおやの乱暴な演奏は“無秩序”の状態を表しており、それに対して体操の動きは“秩序”の状態を表していた。しかし、鳥笛の音は筆者にとって“剥き出しの音そのもの”であり、筆者が予期していなかった強い意図性を感じさせるものだった。じっさい、この出来事は、私たちの音楽的―療法的関係の新たな出発点となった。
異なる生の様式を感じ取る:生きるための技法としての、なおやの生
その後、なおやの病状は急速に進行し、植物状態に近い状態となった。そのため、療育センターでのセッションから、自宅でのセッションに切り替えた。筆者は、彼の呼吸、覚醒レベル、口の動き、まばたき、目や身体の動き、筋緊張の状態などを彼の表現と捉え、一緒に即興演奏をした。
ここで、生物医学的視点からなおやの生を見れば、彼の動きは全て単なる身体的な反射である。なぜなら彼は、疾病のために、外界への認識や反応がないとされているからだ。この診断によって、なおやは社会的な生から疎外され、「単なる生物学的な生」を生きている存在と見なされてしまう。しかし、そのような状態に置かれた人々が必ずしも単に身体的な生を生きている/生かされているだけの存在とは捉えきれないことを示す研究もある(たとえば、西村2001, Herkenrath 2005)。たとえば、ドイツの音楽療法士アンスゲール・ヘルケンラートは、昏睡患者の微細な身体の動きを単なる身体的反射ではなく、ある行為に対して応答する行為と捉える見方を示している。彼によれば、昏睡患者は固有の性格や意識を持っており、彼ら自身の固有の生の形式のなかで生きる存在である。そのことを、(異なる生の形式で生きている)音楽療法士が知覚できないとしても(Herkenrath, 2005:148)。ヘルケンラートの見方に従えば、なおやの身体的反応を単なる反射ではなく、行為に対する応答と見なすことが出来るだろう。なおやの表現を彼の能動的な応答と捉えることによって、私たちは彼を単なる受動的な患者としてではなく、固有の生の様式の中で生きる存在として見ることができる。ヘルケンラートは、この固有の生の様式を「生の技法」、すなわち生きるための表現と呼んでいる。クライエントの生のあり方を「生きるための表現」として捉えることは、クライエントとセラピストが「表現する主体」として、互いに応答し合っていくことを意味する。このことは、音楽作りのプロセスにおける協働へとつながるだろう。
異なる生の様式をつなぐ:音楽紙芝居
ある日のセッションで、なおやと彼の母親、いとこの家族たちと一緒に、音楽紙芝居作り2の活動を行った。あらかじめ、なおやの幼少期~現在までの写真を母親に選んでおいてもらい、拡大コピーして紙芝居の台紙に貼り付けたものを用意した。あわせて、母親やいとこたちに一枚ずつ画用紙を渡し、なおやと筆者たちが即興演奏している間、自由に絵をかいてもらった。これらの写真と絵をシャッフルし、一枚ずつめくりながら、なおやが主人公のストーリーを皆で作っていった。写真がめくられるたびに、家族から歓声があがり、当時の出来事や思い出が語られた。出来あがった物語は、家族の口癖や当時の出来事が盛り込まれ、実際の記憶と、新たなフィクションのストーリーとが混ざり合ったものとなった。紙芝居のタイトルは「ぼく(なおや)の本当のすがた」に決まり、ユーモラスなテーマソングが作られた。以下は、テーマソングの歌詞である。
「ぼくの本当のすがた」
ぼくは忙しい ぼくは忙しい
浜名湖で ミッション
トマトを奪う スナイパー
帰ってきたら ミルクをあげて お花に水やり
「でも、本当は、ぼくは殿様なんだ!」
みんなを 幸せに みんなで幸せに
「これにて、一件落着!」
この創作紙芝居は、なおやの生の様式、家族の生の様式、家族の記憶、絵や写真からの自由な連想、参加者やセラピストの音楽的アイデアといった、様々な異なる表現の様式から成り立っている。したがって、この活動は、異なる生の様式をつなぐ仕掛けとなったのではないかと思われる。
物語創作の過程では、なおやと家族が生きてきた現実のストーリーが想起されると同時に、家族の新たなストーリーが語られた。地理学者のティル・カレンは、場や集団に関する記憶の語り直しの作業を「メモリーワーク」と呼んでいる。彼女によれば「過去の暴力や不当な行為を再度思い返しながら、その喪失やトラウマを克服し、近い未来をより社会的なものとして思い描くようにしていくプロセス」を意味する(Till 2008: 110)。この見方に従うならば、なおやと家族による物語創作の過程は、病に関するある種のメモリーワークとして捉えられるのではないかと思われる。それは、“みんなを幸せに”するなおやの生の様式を、彼の“本当のすがた”として肯定すると共に、“みんなで幸せに”生きる意志を確認する家族の儀式となったのではないかと考えられる。家族にとっての“本当のなおやの姿”は、今でもなお、面倒見のよい兄貴分なのである。
多様な生のあり方、コミュニケーションの多様性へ向けて
本論では、生政治の概念と関連付けながら、音楽療法の場における権力関係の問題について論じてきた。上述したように、生物医学モデルであれ、社会文化モデルであれ、音楽療法士が生権力から逃れることの出来るような、ユートピア的な外部は存在しない。あるとすればそれは、目の前にある対象者の生と向き合い、協働して新たな生の様式を創造していくことしかない。フーコー(Foucault1992)は、このように新しい生の様式を創造していく実践を「生存の技法」(芸術作品としての生)と呼んでいる。彼は、生存の技法を「人々が、自身がどうふるまうかの規則を定めるだけでなく、固有の存在しての自分自身になっていくことを目指して、自らの生をある種の美的価値と様式をもった芸術作品へと作り上げていくような、内省的で意志的な実践」だとしている(ibid. 10-11)。このことをクライエントとの実践で行うために、音楽療法士は、自身の専門家としてのアイデンティティーが守られない地点に身を置いて、そこでの個としての経験を語っていかなければならない。これは「治療ありき」の語りではなく、専門性という衣服を脱いで、個人の感覚経験の主観的現実に即して臨床の音楽行為を捉え直そうとする試みである。自己の感覚経験を見据え、他者との関係性を立ち上げなおしていくことが、あらかじめ決められた「コミュニケーション=音楽の体制」から、生とコミュニケーションの多様なあり方へと向かう、小さな一歩となるだろう。
[1]中枢神経系において脱髄や神経細胞の変性、副腎の機能不全等を伴う、男性におこる遺伝性疾患。小児で発症する場合は、知能低下(学力の低下)、行動の異常(学校の落ち着きのなさ)、斜視、視力・聴力低下、歩行時の足のつっぱりなどの症状で発症することが多い。症状は進行性で、コミュニケーションが取れなくなり、通常1~2年で臥床状態となる。原因・治療法共に確立されておらず、国の特定疾患に指定されている。難病情報センター http://nanbyou.or.jp/sikkan/109_2.htm
[2] この活動では、音楽家・美術家である須崎朝子と林加奈による創作紙芝居の手法(須崎・林 2012)を参考にした。
参考文献
Baines, S. (2013). Music therapy as an anti-oppressive practice. The Arts in Psychotherapy, 40(1), 1-5.
Foucault, Michel. (1990). The history of sexuality (Vol. 1: The will to knowledge). Penguin Books. [フーコー、ミッシェル(1986)『性の歴史Ⅰ:知への意志』、新潮社].
Foucault, Michel. (1992). The History of Sexuality (Vol. 2: The use of pleasure). Penguin Books. [フーコー、ミッシェル(1986)『性の歴史Ⅱ:快楽の活用』、新潮社].
Hadley, Susan. (2013). What we hear/ What we see: Subjugating narratives and liberatory practices. Keynote on the 9th European Music Therapy Congress in Oslo, Norway. Book of Abstracts.
Headlam, Dave. (2006). Learning to hear autistically. In N. Lerner & J. N. Straus (Eds.), Sounding off: Theorizing disability in music (pp. 109-120). New York: Routledge .
Herkenrath, Ansger. ( 2005). Encounter with the conscious being of people in persistent vegetative state. In David Aldridge (Ed.), Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health (pp. 139-160). London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Higashida, Naoki. (2012). 『風になる:自閉症の僕が生きていく風景』ビッグイシュー日本 [Becoming a wind: Landscape in living with Autism]. 132-133頁 [Big Issue Japan, 132-133].
Linton, Simi. (1998). Claiming disability: Knowledge and identity. New York University Press.
Malloch, Stephen, & Trevarthen, Clowyn, (Eds.). (2009). Communicative Musicality: Exploring the basis of human companionship. Oxford University Press.
Murakami, Yasuhiko. (2008). 『自閉症の現象学』勁草書房 [Phenomenology of Autism]. Keisou-Syobo.
Nishimura,Yumi. (2001). 『語りかける身体:看護ケアの現象学』、ゆみる出版 [The telling body: Phenomenology of nursing-care]. Yumiru-Publishers.
Nomura, Makoto. (2009). 「音楽の未来を作曲する、 [Composing outdoor music]. 第13回:野外楽を作曲する」 [Composing the future of music, vol. 13.] Retrieved from: http://www.shobunsha.co.jp/?page_id=1966
Stige, Brynjulf, & Aarø, Leif. Edvard. (2012). Invitation to community music therapy. Routledge.
Straus, Joseph N. (2011). Extraordinary measures: Disability in music. Oxford University Press.
Suzaki, Asako, & Hayashi, Kana. (2012).『創造性を育む音楽あそび・表現あそび:毎日の活動から発表会まで』 [Musical and expressive playing nurturing the children's creativity: from daily activities to school recital]. Ongakuno-tomo-sha.
Till, Karen. E. (2008). Artistic and activist memory-work: Approaching place-based practise. Memory Studies 1(1), 99-113.