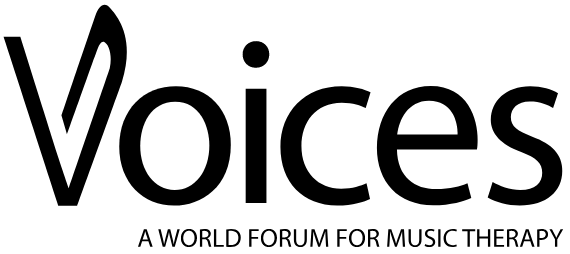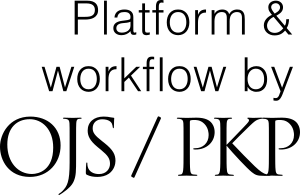[Original Voices: Essay]
EBPムーブメントは,音楽療法にとって本当に脅威なのだろうか?
By Masako Otera
Abstract
本稿では,音楽療法におけるエビデンスに基づいた実践 (Evidence-based practice: EBP in music therapy) について,EBM (Evidence-based Medicine: EBM) にまつわる誤解や様々な解釈,心理学領域におけるEBPの問題に関する斎藤の論考を参考にしながら議論を行っていく。EBPの流れは,音楽療法にとって脅威として受け取られる傾向にあったものの,近年のEBMやEBPに関する議論は,音楽療法におけるEBPを考えるにあたり有利に働くものである。本稿は,多様なエビデンス,臨床能力,クライエントの個別的ニーズを統合することがEBPであるというコンセンサスがすでに形成されていることを示す。その一方で,無作為割り付け試験 (Randomized-Controlled Trials: RCT) や標準化された介入プロトコールの導入については,未だに難しい問題を残していることについても言及する。EBPは,非常に複雑で個々のバイアスに左右されやすい問題である。したがって,音楽療法士が,EBPについて注意深く学び,効果的にEBPを取り入れていくことは音楽療法に利益をもたらすことになる。筆者は,EBPを効果的に導入することを支持する立場であり,そのための理論や方法論の構築が急務であると考える。
キーワード: evidence-based practice, evidence-based medicine, randomized controlled trial
米国音楽療法協会 (American Music Therapy Association: AMTA) は,2010年にエビデンスに基づく音楽療法実践 (Evidence-Based Music Therapy Practice: EBMTP) を「エビデンスに基づく音楽療法実践とは,最良のエビデンスと,音楽療法士の専門技能,およびクライエントのニーズ,価値,好みなどを統合することである (筆者訳)」と定義した (AMTA, 2010)。この定義によれば,音楽療法におけるEBPとは,研究の結果だけでなく,臨床家の専門性やクライエントの個別的なニーズを統合した臨床判断に基づく実践ということになる。
この定義を音楽療法という領域の専門性を反映した,より具体的で明確なものにしていく必要がある。Bradt (2008) は,EBPに関する積極的な議論を音楽療法士に呼びかけた。本稿はこの呼びかけに対して前向きに応じるものであり,EBPに関する共通理解を深めることを期待するものである。Bradtが述べるように,このEBPの問題については,音楽療法にEBPを導入するか否か,ということではなく,EBPをいかに導入するかという問題となりつつあると筆者は考える。そのためには,音楽療法士はEBPについてさらに学ぶ必要がある。それは,他領域におけるEvidence-based medicine (EBM) やEBPをめぐる混乱の歴史を踏襲しないようにするためである。
筆者は,音楽療法におけるEBPを議論するにあたり,斎藤の論考 (2012a, 2012b) が非常に参考になると考えた。斎藤は,日本で医師および研究者としてナラティブに基づく医療 (Narrative-based medicine: NBM) を積極的に推進している。NBMでは,医療実践における患者と医療者の間の物語と談話を重視するので,エビデンスに基づく医療 (EBM) と対立する考え方としてとらえられがちである (斎藤 & 岸本, 2003)。しかし斎藤 (2012b) は,「EBMもNBMも,『個々の患者に最大の幸福をもたらすことを目的とした,医療・医学における理論・方法論である』」(p. 16) とし,EBMとNMBを「車の両輪」(p. 74) として表現している。筆者は,斎藤の考えに強く賛同する。したがって,本稿では,医学vs. 音楽療法,量的研究vs. 質的研究といった,二項対立的な議論を意図的に回避する。そして,斎藤の議論を音楽療法におけるEBPに関する議論を促進するために有効に活用することを目指している。
次項より,まずは,EBMにおける様々な誤解や解釈,そして,心理学領域におけるEBPをめぐる問題について斎藤の論考を紹介する。その後,音楽療法におけるEBPに関する過去の論考を取り上げながら,今後の音楽療法におけるEBPに関して議論を進めていきたい。
EBMにおけるエビデンスをめぐる誤解
EBPとは,本来様々な領域における実践を指すものなので (斎藤, 2012a),EBMもEBPの一環であると考え,EBP in medicineというふうに表現することもできる。しかし,EBMという表現が一般的なので,本稿では医療におけるEBPを従来通りEBMと表記する。
もともとEBPとはEBMから発展した概念であり,EBMは1990年代初頭より提唱され始めた (Straus, Glasziou, Richardson, & Haynes, 2011; 斎藤, 2012b)。EBMの発展の歴史については,本稿の射程範囲外なので取り扱わないことをあらかじめお断りしておく。EBMの当初の目的の1つは,研究で得られた結果を実践に還元することだったが,EBMの解釈について様々な誤解や批判が巻き起こるという結果となった (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996; 斎藤, 2012b)。Sackettら (1996) は,「Evidence based medicine: What it is and what it isn't」という論文を発表し,「個々の患者へのケアについての臨床判断において,最新・最良のエビデンスを,誠実に明示的に思慮深く用いること」(p. 71) 註1というEBMの定義を提唱した。その後,Strausら (2011) が「EBMとは,臨床実践において,エビデンス,患者の意向,臨床能力の三者を統合することである」(p. 1) 註2という定義を発表し,この定義はEBMの標準的教科書の1つである「Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM (Fourth edition)」の冒頭に掲載されている。
斎藤 (2012b) は,EBMにおけるエビデンスの質をめぐる誤解について3つのパターンが存在すると述べている。1つめのパターンは,「エビデンスの階層表を無視して,伝統的に『科学的』と言われてきたような情報,例えば動物実験や研究室レベルにおける基礎科学的な実験的研究から得られたデータを『質の高いエビデンス』と見なしてしまうことである」(p. 21)。EBMは元来,臨床疫学研究の結果を実践に還元することを目指しているので,基礎研究の価値はEBMにおいて低いと見なされるにも関わらず,こうした誤解が存在することを斎藤は指摘している。2つめのパターンは,「判断の根拠とされる情報が数量的に表現されてさえいれば,それは質の高いエビデンスとする考え方である」(p. 21)。斎藤は,数量的に表現された情報の信頼性は,統計学的な吟味によって担保されるのであって,単に情報が数量化されていることだけで,その情報への信頼性は担保されないと述べている。3つめのパターンは,「無作為割り付け試験 (RCT) のみが意味のあるエビデンスであって,それ以外の情報は意味がないとするような,極端な理解の仕方である」(pp. 21-22)。斎藤によれば,EBMとはそもそも個別実践のことであり,個々の実践における最適なエビデンスは異なる。つまり,エビデンスの質の階層も個々のケースによって変わるわけなので,RCTの結果が必ず最適なものであるとは限らない。上述のEBMの標準的教科書の著者であるStrausら (2011) も,「EBMの推奨者であれば,臨床判断の材料として,いくつかのエビデンスのソースが必要なことを認めるだろう (筆者訳)」(p. 7) と述べている。さらに,RCTやシステマティックレビューの結果は,ある特定の疾患に対してある特定の治療法が有効であるか否かということを知りたい場合には最も有効なソースとなり得るが,「それらは,診断,予後,また有害事象については最も有効な答えだとはいえない (筆者訳)」(p. 7) と指摘している。
さらに,斎藤 (2012b) は治療ガイドラインに関する誤解についても言及している。治療ガイドラインとは,あくまでも臨床判断における1つの材料にすぎないにも関わらず,ガイドラインに沿って治療を行うことがEBMの実践であるという誤解が存在する。こうした誤解は,臨床実践を拘束するものであり,患者にとって不利益に働く。また,この誤解は,「EBMの実践は,ワンサイズフィッツオールアプローチではない」註3とする考えからも外れてしまっているのである。
EBMをめぐる様々な解釈
次に,EBMについての様々な解釈に関する斎藤の論考 (2012b) を紹介していく。斎藤は,解釈を3つのタイプに分けて説明している。これら3つの解釈は,共通部分も多いのだが,強調する点がそれぞれ異なるというところがポイントである。
第1の解釈タイプは,「EBM 正統派」(斎藤, 2012b, p. 29) である。EBM正統派は,臨床的疑問の定式化から始まる5段階ステップの実践を重要視する。「PICO」または「PECO」(Straus et al., 2011, pp. 15-16; 斎藤, 2012b, pp. 31-32) は,臨床的疑問の定式化に必要な要素である,「P, Patient」「I or E, Intervention or Exposure」「C, Comparison」「O, Outcome」の頭文字をとったものである。これらの要素に基づき臨床的疑問を定式化した後に,さらに4つのステップ,1) 問題についての情報収集,2) 得られた情報の批判的吟味,3) 得られた情報の患者への適用,4) これまでの実践の評価, を実践する (斎藤, 2012b, p. 31)。EBM正統派は,EBM教育において最も標準的な考え方とされている。
第2の解釈タイプは,「EBMガイドライン派」(斎藤, 2012b, p. 30)である。EBMガイドライン派の考え方は,臨床疫学的な情報とそれらの批判的吟味を行うという点では,EBM正統派と共通する。しかし,EBMガイドライン派は,「エビデンスを収集してそれに基づいた診療ガイドラインを作成し,それを医療実践に普及させること」(p. 32) を何よりも重視する。この目的を達成するためには,エビデンスの質の階層の作成が重要となる。エビデンスの質の階層では,RCTで得られた結果が最もレベルが高く,症例報告や専門家の意見はレベルが低いものとしてランク付けがなされている。こうしたランク付けを行い,エビデンスの推奨レベルを設定することで,EBM正統派の批判的吟味に耐えることができないエビデンスを複数あるエビデンスの1つとして位置づけることが可能となるわけである。
第3の解釈タイプは,「EBM伝統科学派」(斎藤, 2012b, p. 32) である。EBM伝統科学派は,エビデンスの科学性と医学研究における客観性を何よりも重視する。科学性とは,「物事を実証的,組織的に取り扱うといった,科学の分野で求められるような態度や傾向」(日本国語大辞典, n.d.) のことである。EBM正統派とEBMガイドライン派は,臨床疫学研究の結果をエビデンスとして採用するのに対して,EBM伝統科学派は,生体科学や病態生理学的な基礎医学研究の結果もエビデンスとして採用する。また,心理的状態やQOLといった主観的な指標は,たとえそれが数量的に表現されていたとしても,エビデンスとしては認められない。
斎藤 (2012b) は,こうしたEBMに対して異なる強調点を持つにいたるのは,人々の異なる観点によるものだと述べる。例えば,自らが作成したガイドラインの普及を臨む人々は,EBMガイドライン派の考え方に,科学研究における科学性を厳密に追求する立場の研究者は,EBM伝統科学派の考え方にそれぞれ賛同するだろう。それぞれの立場によって異なる観点を持つことは避けられない上に,どの観点が最も正しいかということを追求することは不毛な議論を呼ぶだけである (斎藤, 2012b)。
今のところ,EBMでは量的研究によって得られた臨床データがエビデンスとして主に採用されている。その一方で,上述のEBMの教科書では,質的研究についてもセクションを設け,質的研究は,「患者の経験や価値に重きをおいた臨床的事象を理解するために役に立つだろう(筆者訳)」(Straus et al., 2011, p. 110) と述べている。斎藤は,「患者が病いをどのように経験し,それをどのように意味づけるか」ということを知ることは,「患者のアウトカム (治療効果) と切り離せない」(斎藤, 2012b, p. 22-23) と指摘している。また,斎藤は質的研究によって得られた結果をエビデンスとして用いるための方法論の必要性についても言及している。
心理学におけるEBPとEmpirically supported treatments の問題
米国では,心理学領域におけるEBP (Evidence-based practice in psychology: EBPP) の歴史おいて,様々な混乱と誤解が生じた。斎藤 (2012a) は,EBPPの発展において大きな問題となったのが,「Empirically Supported Treatments (ESTs)」であると解説している。1990年代初頭に,米国心理学協会 (American Psychological Association: APA) は,ESTsの作成に着手した。ESTsとは,実証的研究によって治療効果が支持された治療法と標準化された治療手続きのリストである。結果的に,認知行動療法をベースとした治療法がリストを独占することとなり,それ以外の治療法にとって不公平な状況を生み出したばかりでなく,EBPPとはESTsにリストアップされている治療法の実践のことを指すという印象を与え兼ねない事態となってしまった (斎藤, 2012a)。
APA (2006) は,近年になってEBPPとESTsの概念的違いについて解説している。それによれば,ESTsは,ある特定の臨床症状に対する,ある特定の治療法の効果を問うものであるのに対して,EBPPはあくまでも個々の臨床実践に多様なエビデンスを統合していくプロセスのことを指している。つまり,EBPPとはESTsの上位に位置する概念であり,ESTsとはある実践ケースに対する治療的選択肢の一つにすぎないということである。また,APAは実証的に検証されたことがない治療法は効果がないと証明された訳ではないという点についても強調している。
APA (2006) は,「efficacy, effectiveness, cost-effectiveness, cost-benefit, epidemiological, treatment utilization (p. 274)」など,エビデンスの多様性を提唱した。また,こうした多様なエビデンスを得るための多様な研究デザインの必要性にも言及しており,質的研究もその中に含まれている。APAは,「心理学の実践とは,治療的効果における多様な相互作用性について臨床的にも研究的にも着目する必要のある複雑な関係性と技術性を含む営みである (筆者訳)」(p. 275) と述べている。このようにEBPPとESTsの歴史は,心理学の実践が包括的実践の方向に向かっていることを示唆しており,これは特定のエビデンスのみを採用しようとする流れとは反対方向に向かっているといえる。
音楽療法におけるEBP
斎藤の議論 (2012a, 2012b) をふまえて,ここからは音楽療法におけるEBPに関する議論に移る。AMTAが,エビデンスに基づいた音楽療法実践に関する定義を提唱する10年以上前に,Madsen & Madsen (1997) は,音楽療法における音楽の療法的応用は科学的なエビデンスに基づいている必要があると述べている。彼らの考えは,音楽療法士が音楽療法の効果を問われたときにどのように回答するかという問題について述べられたものであり,EBMやEBPの文脈でなされたものではない。しかし,彼らの言及はその後のEBPをめぐる問題を予見するものであったといえるだろう。また,量的研究と質的研究をめぐる大論争がなされたことは言うまでもない (e.g. Rolvsjord, Gold, & Stige, 2005)。
Vink & Bruinsma (2003) は,音楽療法における説明責任という意味におけるEBPの重要性を強調している。彼らは,音楽療法の有効性を他領域に示すために,特にコクランライブラリーによるシステマティックレビューによって科学性が担保されたエビデンスとエビデンスの質の階層の採用の重要性を主張した。彼らの論文では,上述の5つのステップによるEBMの実践とその結果得られた彼らの臨床判断が提示された。彼らは,質的研究による研究結果をエビデンスとして除外しなかったものの,どちらかといえば,それらを量的研究結果の補助的役割として位置づけていた。彼らの考え方は,上述のEBMの3つのタイプ解釈の全てを兼ね備えたものであり,EBMの方法論を音楽療法にそのままあてはめようとしたものであった。こうした考え方に対して,多くの臨床家や研究者が音楽療法にEBPを導入することに対して不安感や恐れを表明した。
Aldridge (2003) やEdwards (2004) は,エビデンスを量的研究結果のものだけに限定することや,標準化された治療プロトコールの使用について異論を唱えた。O’Callaghan (2005, 2009) とEdwards (2004) は,音楽療法における対象者の多様性,そして実践における個別性と柔軟性を理由に,緩和ケアや小児科領域における音楽療法研究にRCTを適用することの困難性を指摘している。彼らによって指摘された問題点は,多彩な対象者層を扱う音楽療法士にとって共通のものであるといえるだろう。
ここまでの議論をまとめると,主に2つの問題点が浮上し,それらについて議論してきたことになる。まず1つめは,エビデンスの種類をある特定のものに限定するということの妥当性についてである。2つめは,音楽療法のRCTを実施することの難しさである。2つめの問題点は,困難な問題として残らざるを得ないが (この問題については後述),1つめの問題については,もはやそれほど大きな問題ではないのかもしれない。なぜなら,多様なエビデンスを臨床家の専門性とクライエントの個別性に統合するということがすでにEBPのコンセンサスとなっているからである。また,EBPとはあくまでも個別実践を指すので,標準化された治療法への過度な依存を意味するものではない。Bradt (2012) は,EBPとは,RCTとメタアナリシスの結果から構成される「生化学的階層的モデル (筆者訳): the biomedical hierarchical model」だと述べ,こうしたモデルは音楽療法に不適応だと批評している。筆者は,そうしたモデルが音楽療法に不適応だという点には同意するが,EBPをそのように固定的に理解することについては疑問視している。なぜなら,EBPの射程範囲は広がりを見せており,エビデンスの多様性について柔軟性をもって対応しようとする方向性に開かれていると考えるからである。
音楽療法におけるEBPの今後
音楽療法におけるこのEBP問題に音楽療法はどのように対処してゆけばよいのだろうか?まず,エビデンスの多様性を基礎づけるためにAbrams (2010) が行ったような理論研究が必要である。ただ単にエビデンスの多様性を訴えるだけでは,特定のエビデンスしか認めない人たちを納得させることはできないからである。こうした理論研究を行うための認識論的枠組みも必要である。多様なエビデンスを認めるということは,異なる認識論の存在を同時に認める必要性が生じるからである。認識論とは,「認識の期限・本質。妥当範囲を論究する哲学の一部門」(広辞苑, n.d.) のことである。
京極 (2006) は,構造構成学をメタ理論的枠組みとして用いて,EBPにおけるエビデンスの多様性の基礎づけを行った。構造構成学とは,西條 (2005) によって創唱された新たな哲学である。構造構成学では,この世の全ての事象は立ち現れた現象から構造化されると規定している。例えば,「死にそうなほど喉が渇いていたら『水たまり』も『飲料水』という存在(価値)として立ち現れることになる」(西條, 2005, p. 53) と西條が例示しているが,「水たまり」と「飲料水」が,この例における「構造」である。つまり,我々を取りまく全てのモノやコトは,立ち現れた現象の中から各人の関心・志向性に相関して構造化された結果だということであり,そのような「構造」の多様性は避けられない。京極はこの原理を用いて,エビデンスの多様性の存在を基礎づけると同時に,それら多様なエビデンスの有用性は実践の目的によって変わりうるものだということも理論化した。筆者は,京極の研究は音楽療法におけるエビデンスの多様性の問題に対して有用性が高いと考えるが,これに関する議論は他稿にて行いたいと考える。
EBPに関する議論を行う際には,自らの立場を明示化して行うことが重要である。異なる立場の人々の間でEBMに対する関心と期待のポイントが異なり,それがもとで誤解が生じたり,様々な解釈がなされていたりすることはすでに述べた通りである (斎藤, 2012b)。同じ問題はEBPでも起こりうる。例えば,研究者,臨床家,病院や公的施設の管理者は,それぞれの関心に基づいたEBPに対する見解を持っている。すなわち,それぞれの立場に有利になるようにEBPを理解しようとするのは自明である。EBMの議論における自らの考えについて今一度立ち返り,その上で自らの立場を表明することは,自分自身にとっても有益であるだけでなく,他者の立場を理解する助けとなり,その結果不毛な議論の応酬を回避することにつながる (京極, 2011; 西條, 2005)。また,各人が異なる立場にあったとしても,EBPとはそもそもクライエントの利益に資するためのもの, ということを音楽療法士の間で共通了解事項として共有しておくことが重要であることは言うまでもない。
斎藤 (2012b) は,「臨床判断・決断の過程を明示的に示す」(p. 37) ことはEBMにおいて非常に重要だと述べている。クライエントはそうした情報の受け手として最優先されるべきである。そして,音楽療法士はそうした情報の提供者としての責任を負っている。専門職として,音楽療法士は,いかなる種類のエビデンスを採用しようとも,どのような状況でどのような援助方法を用いることを決断するに至ったのか,その経緯について説明可能である必要がある。これは,エビデンスの多様性や標準化された治療プロトコールの導入に関する問題とはまた別の問題である。
音楽療法研究においてRCTを実施することの困難性は難問として残る。この問題は,音楽療法の効果を示すということだけでなく,標準化した治療プロトコールを実践に導入するか否かということも含んでいる。Rolvsjord, Gold, & Stige (2005) は,標準化された治療プロトコールを使用する代わりに「a contextual approach to resource-centered music therapy」(p. 17) の原理を反映させたガイドラインを, 彼らのRCTに活用する方法を考案した。筆者は,音楽療法実践における柔軟性と自然発生的な性質をRCTによって殺さないようにするために行った彼らの工夫について敬意を払う。しかし,彼らのガイドラインの使用は,研究の背景となる認識論における問題を克服していない。RCTとは,客観主義に基づいた研究方法論である(Bruscia, 1998; 京極, 2006)。客観主義は,主体から独立した形での外部実在を仮定しており,その存在について人々は同じものとして認識していることが前提となっている。したがって,客観主義に基づく研究では,そうした外部実在同士の関係性を検証することが可能となる。つまり,標準化された治療プロトコールが対象者に対して効果があったのか否かということの検証に適しているのである。ところが,Rolvsjord らが採用するガイドラインは,構成主義に基づいており,RCTの認識論的背景となっている客観主義とは相容れない。構成主義では,外部実在の存在を認めず,そうした存在は全て各人によって構成されると規定しているからである。したがって,ある特定の介入法の効果を検証する場合は,RCTを行うことが最も適切な方法ということになる。音楽療法におけるRCTの問題に関する筆者の見解は,標準化することが可能なプロトコールのみを対象としてRCTを行うというものである。これにより,限られた介入法のみがRCTの対象となることは避けられない。それでもなお,これらの介入法の効果を知ることは,音楽療法士のみならずクライエントの利益となる。何よりも大切なことは,EBPPにおけるESTsをめぐる問題から学び,RCTで得られた結果以外の介入方法は効果がないものとして取り扱わないようにすることである。また,エビデンスの多様性を裏付ける理論研究を充実させることも重要である。
斎藤 (2012a, 2012b) の議論が示すとおり,EBPをめぐる問題は非常に複雑であり,かつ立場の違いから様々な偏見にさらされやすい。したがって,音楽療法士は注意深くかつ積極的にEBPについて学ぶ必要がある。そうした効果的な学びは音楽療法におけるEBPに関連する研究をより促進することにつながる。EBPが音楽療法にとってリスクとなるのか利益となるのかは,音楽療法士がこのEBPの問題にどのように対処するかにかかっているのである (Bradt, 2008)。
結論
本稿では,EBMをめぐる誤解や様々な解釈,またEBPPにおけるESTsの問題などに関する斎藤の議論 (2012a, 2012b) を参照しながら,音楽療法におけるEBPをめぐる問題について議論を展開した。EBPのムーブメントは,音楽療法にとって脅威としてみなされる傾向にあったが,本稿ではそのような必要性が低下していることを示した。筆者は,音楽療法士の間で,EBPはクライエントの利益となる実践を提供するためのものであるという共通了解を共有した上でのEBPの推進を支持し,そのための理論研究の充実が音楽療法におけるEBPの推進に寄与すると考える。
1. 日本語訳は,斎藤清二. (2012a).「エビデンスに基づく実践」のハイジャックとその救出. こころの科学, 165, のp. 3を引用した。
2. 日本語訳は,斎藤清二. (2012a).「エビデンスに基づく実践」のハイジャックとその救出. こころの科学, 165, のp. 3を引用した。
3. 「ワンサイズフィッツオール: One-size fits all」とは,日本語の「フリーサイズ」のことを指す。つまり,1つの基準が何にでも適応可能である状態を表現している。
References
Abrams, B. (2010). Evidence-based music therapy practice: An integral understanding. Journal of Music Therapy, 47(4), 351-379.
Aldridge, D. (2003). Staying close to practice: Which evidence, for whom, by whom. Music Therapy Today 4(5). Retrieved Oct 23, 2012, from http://www.wfmt.info/ Musictherapyworld/modules/mmmagazine/issues/20040727092613/20040727093052/MTT5_4_Edwards.pdf.
American Psychological Association. (2006). APA Presidential task force on evidence-based practice. American Psychologist 61(4), 271-285.
Association, A. M. T. (2010). Definition: Evidence-based music therapy practice (EBMTP) Retrieved Jan 18, 2013, from http://www.musictherapy.org/research/ strategic _priority_on_research/evidencebased_practice/.
Bradt, J. (2008). Evidence-based practice in music therapy: Let's continue the dialogue Voices: A World Forum for Music Therapy. Retrieved March 18, 2013, from http://voices.no/?q=colbradt210408.
Bradt, J. (2012). Randomized controlled trials in music therapy: Guidelines for design and implementation. Journal of Music Therapy, 49(2), 120-149.
Bruscia, K. (1998). Defining quantitative and qualitative research. Defining music therapy (2nd Ed, pp.254-260). NH: Barcelona.
Edwards, J. (2004). Can music therapy in medical contexts ever be evidenced-based? Music Therapy Today, 5(4). Retrieved Oct 23, 2012, from http://www.wfmt.info/ Musictherapyworld/modules/mmmagazine/issues/20040727092613/20040727093052/MTT5_4_Edwards.pdf .
かがくせい【科学性】, 日本国語大辞典, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース), http://www.jkn21.com,アクセス日,2013年5月30日.
京極 真. (2011). 医療関係者のための信念対立解明アプローチ コミュニケーション・スキル入門: 誠信書房.
京極真. (2006). EBR(evidence-based rehabilitation)におけるエビデンスの科学論-構造構成主義アプローチ. 総合リハビリテ-ション, 34(5), 473-478.
Madsen, C. K., Madsen, C.H.Jr. (1997). Music as an art and a science. In Experimental research in music (3rd ed., pp. 8-9). NC: Contemporary Publishing.
にんしきろん【認識論】,広辞苑,第五版[電子辞書],カシオ.
O'Callaghan, C. (2005). The contribution of music therapy to palliative medicine. In D. Doyle, Hanks, G., Cherny, N., & Calman, K. (Ed.), Oxford textbook of palliative medicine (3rd ed., pp. 1041-1046). Oxford: Oxford University Press.
O'Callaghan, C. (2009). Objectivist and constructivist music therapy research in oncology and palliative care: an overview and reflection. Music and Medicine, 1(1), 41-60.
Rolvsjord, R., Gold, C., & Stige, B. (2005). Research rigour and therapeutic flexibility: rationale for a therapy manual developed for a randomised controlled trial. Nordic Journal of Music Therapy, 14(1), 15-32. doi: 10.1080/08098130509478122
Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't - It's about integrating individual clinical expertise and the best external evidence. British Medical Journal, 312(7023), 71-72. doi: 10.1136/bmj.312.7023.71
斎藤清二. (2012a). 「エビデンスに基づく実践」のハイジャックとその救出. こころの科学, 165, 2-8.
斎藤清二. (2012b). 医療におけるナラティブとエビデンス : 対立から調和へ. 遠見書房.
斎藤清二 & 岸本寛史. (2003). ナラティブ・ベイスド・メディスンの実践. 金剛出版.
西條 剛央. (2005). 構造構成主義とは何か 次世代人間科学の原理. 北大路書房.
Straus, S. E., Glasziou, P., Richardson, W. S., & Haynes, R. B. (2011). Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM (4th ed.). Edinburgh: Churchhill Livingstone Elsevier.
Vink, A., & Bruinsma, M. (2003). Evidence based music therapy. Music Therapy Today, 4(5). Retrieved Oct 23, 2012, from http://www.wfmt.info/Musictherapyworld /modules/mmmagazine/issues/20031103132043/20031103132433/DA_Nov03.pdf.