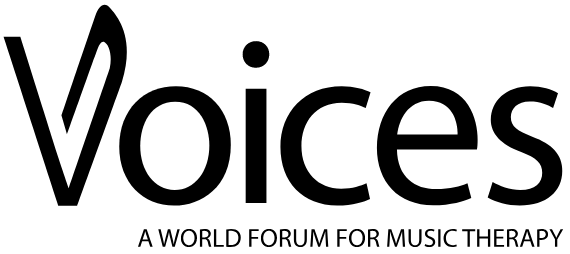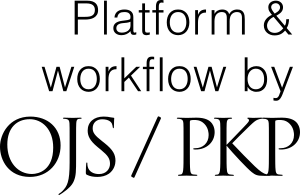第2次世界大戦の影
寒い冬の午後、町の東にある老人ホームにシェンを訪ねた。ベタベタした床、やむことのないベルの音、息苦しい雰囲気を思い出す。シェンの部屋はナースステーションから廊下を横切った、落ち着きの無い場所にあった。私が訪ねた時、シェンは車椅子に座ってテレビを見ていた。大抵の入居者とは違って、シェンの部屋は個人部屋。床の代わりに青いカーペットが部屋を明るくしていた。
自己紹介をし、ホスピスから来たミュージックセラピストだと説明すると、シェンは笑顔をみせた。黒ぶちメガネをかけ、きちんと洋服を着ていたが、シェンはやせ細っていた。
「今日はあなたが音楽を聞きたいかと思って、訪ねました。」
と言うと、シェンは
「音楽は好きです。合唱団や聖歌隊でずっと歌ってきました。」
と言った。
「どんな音楽が好きですか?」
「なんでも好きです。」
シェンは脳腫瘍のためしゃべり方は遅かったが、意識ははっきりしていた。控えめでやさしい話し方をする、穏やかな人だ。
何週間か前、同じ老人ホームに違う患者さんを訪問している時、ホスピスの看護助手、ワンダに呼び止められた。
「新しい患者さんがいるの。いい人なんだけど、あまり話をしないし、とても大人しいの。でも、ユミとなら話すと思う。2人ともアジア人だから。シェンは中国系だと思う。」
ワンダが言った。彼女は私が日本人だという事や、日本と中国が難しい歴史関係にあった事を知っているのだろうか。この場合、私がアジア人だという事がいい影響を与えるかどうかはわからないということを、ワンダには言わなかった。その後すぐホスピスの看護師から、シェンには意味のあるアクティビティーが必要、という理由でミュージックセラピーを委託された。
シェンの反応を見るため、中国の民謡を含めたさまざまな曲を弾いた。私がギターを弾く手をじっと見ながら、シェンは静かに音楽を聴いた。どの曲に対しても、「いいね。」といい、笑顔を見せるシェン。
「今弾いた曲、聴いたことありますか?」
「うん、いくつかは聴いた事がある。中国の曲よりアメリカの曲の方が覚えてる。中国を離れたのは随分昔だからね。」
と言って、シェンは人生のこれまでを語り始めたのだった。
「生まれは中国の福州。14歳の時に家族とアメリカに旅行に来て、中国に帰れなくなった。政治的な理由でね。」
その理由を具体的には話さないまま、シェンは続けた。
「その後すぐ、大学の教授だった父親は病気で死んだんだ。」
「若いときに父親を亡くして大変だったでしょうね。」
「そうだね。でもそれは乗り切らないといけない事だった。」
シェンと妹は母親に育てられた。誰も知らない異国の地で生活を始めるのには、大変な苦労があったという。淡々と人生を振り返るシェンだったが、その背後に未だ解消されていない気持ちが見え隠れしていた。
「その後、中国に帰りましたか?」
「1回だけ。娘が中国で結婚した時にね。」
「どうでしたか?」
「良かったよ。見たことのない物が沢山見れた。でも、福州に行く時間はなかったんだ。」
シェンはそう言って、静かになった。
その夜、家に帰って福州について調べた。シェンが子供の頃、福州は日本の占領下にあったことを知った。インターネットで検索された写真は、心をかき乱すような映像だった。階段に横たわる女性、男性、子供達の遺体。このような写真は以前見たことがあったし、日本の占領下にあった中国ではひどい事が起こった事は知っていた。シェンは子供の時日本占領下でどういった体験をしたのだろうか。私が日本人という事がセラピー上の信頼関係にどういった影響を及ぼすだろうか。
数年前ミュージックセラピーのインターンだった頃の事。第2次世界大戦を経験した患者さんは、日本人だという事で、私に対して怒りを感じるかもしれない、とスーパーバイザーが心配した。それに関してどう思うか、と聞かれた時、私はどんなことになるか全く予想できないと答えた。そういった事を考えてなかった自分は認識が足りなかったのかもしれない。第2次世界大戦に行き、滅多にその話をしない祖父の事を考えた。高校卒業後アメリカに行くと決めたときは驚いていた祖父だが、アメリカ人に関して険悪さを見せたことはなかった。第2次世界大戦はずっと昔に起こった事。人はそんなに長い間怒りを抱え続けられるのだろうか?戦争の理由で、患者さんと意味のある関係が作れない、という事があるだろうか?少しづつ見つけたその答えは、予期しないものだった。
ミュージックセラピストになって間もない頃、イタリア系アメリカ人のサムに出会った。90歳代なのに70歳くらいにしか見えないサムは、エネルギーに溢れ、いつも思い浮かんだことをすぐ話すような人だった。フレンドリーな笑顔と明るさで、サムはすぐに病棟の人気者になった。
ある日私がイタリアの曲をギターで弾いていると、サムは自分の子供時代の事や、誇りに思っているイタリアの伝統に関して話し始めた。それがきっかけで、私はどこから来たのか、と聞かれた。日本人だと言うと、サムは突然表情を変え、泣き出した。
「軍隊に入った時、イタリアに行かされる事を願ってたんだ。そうすれば親戚にも会えると思って。でもその代わりに日本に行かされた。」
サムはそう言って、まるで私の事を見るのが辛いかのように、目を閉じた。
「原爆実験に関わったんだ。犠牲になった子供達や、罪のない人達の事を考えると・・・。」
サムは目をそらし、首を左右に振った。
「誇りには思ってない。」
と言ってサムは泣き始めた。
なんと言ったらいいのかわからず、沈黙してベットの隣に座っていると、サムが一生抱えてきた強烈な苦悩と悲しみが伝わってきた。高校の修学旅行で行った広島を思い出した。原爆ドームで見た事は私の記憶に一生残るだろう。体から剥けた状態で壁にくっついた皮膚。階段に残された影。暑い夏日に灰色のスーツを着た、70歳代の被爆者体験者の話を聞いた。原爆の直後あまりにも死者が多かったため、全部遺体を片付けるのは不可能だったと、原爆ドームの前に立っている私達にその人は言った。
「あなた達が立っているそのコンクリートの下には、今でもたくさんの死者が眠っています。」
私はサムとの出会いによって、悲劇のもう1面を目の前にしたのだ。原爆に携わったという罪悪感に一生悩まされたアメリカ復員軍人。サムはあまりの動揺のため、息を切らした。
「大学での原爆実験に関わってたんだ。」
サムはそう言って、ベットから頭を持ち上げた。
「知らなかったんだ。落とすとは・・・、知らなかった。」
サムの目は涙でいっぱいになっていた。胸をつまらせ、これ以上話せないサム。もっと聞きたい事はあったが、質問はしない事にした。泣きながら、サムの貧弱な体が震えた。
しばらくすると、もうこれ以上話したくなかったのか、サムは音楽を聴きたい、と言った。彼の好きなビックバンドの曲を弾くと、サムは頭を枕に下ろして目を閉じた。歌が彼の心を労うように、私はギターを弾きながら歌った。
次の1ヶ月の間、週に一回サムを訪問した。音楽と私の存在が、サムに戦争時代の事を思い出させるようだった。思い出すのは辛いよう だったが、毎回必ず戦争の話になった。具体的な事は話せないまま、毎回同じ事を何度も振り返るサム。
音楽は彼が気持ちを表現できる、安全な空間を作った。サムは昔の懐かしい曲を聴くと泣き、話をするのが辛くなると音楽を聴きたい、と言った。音楽はサムの気持ちを楽にさせ、落ち着かせるようだった。長く充実した人生を送ったサムだったが、たった一つの苦しみは戦争の思い出だった。死が近づくにつれ、1番思い出したくない出来事が、サムの心に浮かんだようだ。
その何年か後、ショートステイで病棟に入院していたジムに出会った。私が訪問した時、ジムは窓際の椅子にすわって外を見ていた。自己紹介をしハープを弾きましょうか、と言うと、ジムはそれに同意。
「どんな音楽が好きですか?」
と聞くと、
「何でも好き。」
と答えた。私がアメリカのフォークソングを弾いている間、ジムは静かだった。彼が何を考えているのかはわからなかったが、何か思いにふけている様子のジム。音楽の後、
「昔戦争中に中国人の女性と出会って、良くしてもらった。君も中国人?」
と聞かれた。
「私は日本人です。」
というとジムは静かになり、下を向いた。
「日本人の軍人を殺した。彼らは若かった。自分も若かった。彼らの家族の事を想う・・・。本当に申し訳ない。」
ジムは言葉に詰まり、それ以上話せなかった。
ジムの突然の告白に私は驚いた。彼の感情は、まるでその事が昨日あったかのように、強烈で痛ましいものだった。彼はこの事を今まであまり人には言わず、一人で抱えてきたのではないだろうか。ジムは感情をこのように表す事によって、少しは楽になるかもしれないと思い、静かに座ったままジムの感情を受け入れた。どれくらいそこに座っていたかは覚えてないが、随分長い時間のように感じた。ジムはようやく泣き止んだが、まだ下を向いていた。
「もう1曲弾きましょうか?」
と聞くと、ジムは
「OK」
と言った。その時思い浮かんだ、シンプルで聞き覚えがある曲を弾くと、音楽が私達の心を落ち着かせるようだった。部屋を立ち去る前、いろいろ話してくれた事をジムに感謝すると、彼は音楽を弾いてくれてありがとう、と言った。
ジムに会ったのはそれが最後だった。ジムとサムは、罪悪感を抱えながら人生を送った人達。殺害の罪、生き残った罪、もしくは後悔が残る事に携わったという罪。彼らと似たような経験がある復員軍人に出会うたびに、2人が語った話を思い出す。復員軍人が人生の最後に思い出す気持ちというのは、勝利の喜びや怒りではない。むしろ強い悲しみ、孤独感、罪悪感に絶えずさいなまれているのだ。
シェンとの出会いによって、戦争中は軍人だけではなく、一般市民も苦しんだ事を思い知らされた。しかし軍人とは違い、シェンのような市民は積極的に戦争に参加したわけではない。その代わりに、シェンは暴力を受ける側だった。だからもしかすると、シェンは復員軍人よりも日本人に対する怒りがあるかもしれない。中国と日本が抱える辛い過去が、私とシェンの関係に悪い影響を及ぼすかもしれない、と気がかりだった。
シェンと初めて会ってから5ヶ月が過ぎた。外の景色は、灰色の空から紫の花や緑に変わっていた。シェンの病気は少しずつ進み、スピーチや動作に影響を与えた。福州での子供時代の事をもっと知りたかったのだが、シェンはあまり覚えていない、と言う。話さない理由というのは、脳腫瘍のせいなのか、それとも思い出したくなかったからだろうか。音楽を使ってシェンに安らぎを与える事と、懐かしい合唱団時代の思い出をよみがえらせる事が、セッションの中心だった。シェンはいつも丁寧で親切だったが、私が日本人であるという事をどう思っているのかはわからないままだった。
そんなある日、思いがけない事が起こった。人を苗字で呼ぶべきか、それとも名前で呼ぶべきか、という話をしていた時の事。シェンは老人ホームのスタッフに名前で呼ばれるのは構わないが、この場合中国の習慣では、苗字で呼ばれる方が望ましい、と言った。
「君もアジア人だからわかるでしょう?」
と言って、シェンは微笑んだ。お互いにアジア人である事に彼が触れたのは、初めての事だったので、私はうれしい驚きを感じた。
「それはわかります。もし私達が中国か日本で出会ったとしたら、苗字で呼ぶ方が普通ですよね。これからは苗字で呼んだ方がいいですか?」
と聞くと、シェンは笑って、
「シェンって呼んでいいよ。」
と言った。このささいなやりとりが緊張感を解いたので、もう少し両国の文化の共通点に関して話をする事にした。
「部屋に中国のカレンダーがいくつかありますね。」
と私がいうと、
「習字が好きなんだ。」
テレビの隣にある漢字のカレンダーを見ながら、シェンは言った。
「漢字はほとんど忘れたけど、今でも・・・好きだから、娘が・・くれたんだ。」
シェンはゆっくりと、はっきりした口調で話した。漢字は使ってないと忘れやすいものなので、シェンの気持ちはよくわかった。日本語を忘れないように、日本語で読み書きをするようにと、父にしばしば言われた事を思い出した。
「漢字を忘れないようにするのは大変ですよね。私も沢山忘れてます。使わないと、忘れますよね。」
と言うとシェンはうなずいた。
「子供のとき、習字を習ってました。」
「本当?」
と言ってシェンが微笑んだ。
「でもその当時は習字が好きではなかったんです。正座をしないとけないでしょう?」
「そうだね」
と言ってシェンは笑った。
「でも、今は習字も好きでたまにやります。1つ1つの漢字に意味があるから、その起源を知るのも面白いですよね。」
自分の名前を漢字で書いてみせると、シェンは、
「いいね。」
と言った。
残りの時間、カレンダーを見ながら漢字の意味について話がはずんだ。お互いアジア人だという事は、シェンとの関係によい影響を及ぼすだろう、と言ったワンダの判断は正しかった。文化と音楽を分かち合う事によって、シェンと意味のある関係を作る事ができたのだと思う。シェンがこういった形で私を受け入れてくれた事にほっとし、忌まわしい過去の歴史から開放され、安らかな気持ちになった。
次のセッションで、シェンに日本の曲を聴きたいか、と聞いてみた。すると、
「もちろん。」
と言うので、日本の民謡、「春が来た」を歌った。
「この歌聴いた事ありますか?」
と聞くと、シェンは首を振ったので、英語訳を教えた。
春が来た、春が来た、どこに来た
山に来た、里に来た、野にも来た
「1度も聴いた事がないが、いい曲だ。」
とシェンは言い、窓の外を見た。
「昔良く・・・いろんな場所に行った。山とか・・・野原に行って、写真を・・・撮った。」
言葉を話すのに大変な努力が必要となった今、シェンはゆっくりと小さな声で話した。この歌が彼の趣味であった写真撮影を思い出せたようだ。シェンはよく外に出たがったが、そうできるのは家族が遊びに来た時だけだった。
「外に行って写真を撮れないのは寂しいでしょう。」
と言うと、シェンはうなずき、何か考えている様子。その時、これは今までずっと聞きたかった事を聞くチャンスだ、と感じた。
「もう知り合ってから5ヶ月経ちましたね。ホスピスの患者さんだっていう事、どう思いますか?」
「死については・・・、時々複雑な気持ちになる。でも、それは・・・なんとか乗り切らないといけない事。」
「乗り切らないといけない事?」
「そう。」
「以前どうやって辛い時代を生き延びたのですか?と聞いた時、同じ事言いましたよね。」
「そのとおり。」
と言って、シェンは笑った。