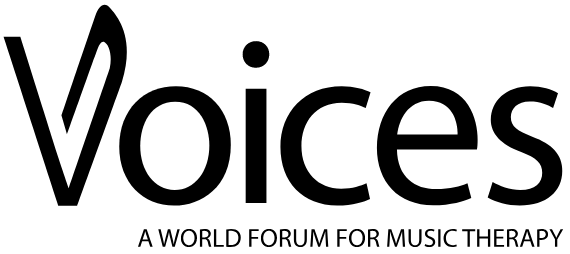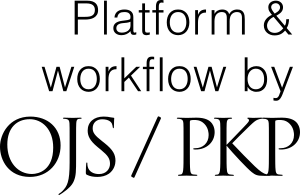日本における音楽療法の現状と展望
1. 日本の音楽療法の急速な発展
巻末の資料にもあるように(日本の音楽療法の現況)、日本の音楽療法は1990年代から2000年初頭にかけて急速な展開を見せた。その結果、一般社会における認知度は上がり、音楽療法を専門とする職業人・学生も多く育ちつつあり、音楽療法の活動は全国規模で広がった。そこにはそれ以前の先輩音楽療法士たちの献身的な努力があり、社会的機運を得て結実したのだと言えよう。
その背景として櫻林は、経済産業の先進社会における非人間的精神環境が人々に療法的ニーズを気づかせたこと、そういった社会で強者の側にいる者が弱者の側にいるものと社会的資源を分かち合おうとする福祉への関心の高まり、そして西洋クラシック音楽教育ブームによる音楽界の飽和的豊熟といったことを指摘している(櫻林、1993, 生野、2002a)。
しかしあまりにも急速であった発展は、当然のことながら副作用ももたらした。つまり、日本の音楽療法はその発展の「芯」となるもの、つまり自らのアイデンティティが十分に成熟していないという側面をもっている。そのために、こうした「社会環境」「福祉」「音楽界」などの周辺的要素にいつも揺さぶられている、言い換えればその一つでも弱まればいつでもバランスを崩す危険があるという見方もできるだろう。
日本の音楽療法は、時流の勢いに乗って成長した時期がそろそろ終わり、さらなる発展のための重要な過渡期を迎えている。こうした中、日本の音楽療法士たちは、日本という文化土壌に向き合いながら生産的な議論を重ね、明確なビジョンを持つ必要に迫られている。
2. 日本の文化:その伝統的、複合的、そして過渡的な性質
さて「文化」と言ったとき、日本において「伝統的」文化だけが重要な役割を果たしているわけではなく、きわめて複合的で過渡的な文化現象がこの社会を支配している。この複合的性質は、恐らくアジアの多くの国で共通するのではないだろうか。例えば、日本人は意識・無意識レベルの両方でその行動様式を規制している伝統的慣習に加え、アメリカ文化の強い魅力からの影響、われわれの両親の世代に指導的役割を果たしたヨーロッパ文化の存在からの重厚な影響、そして特に若い世代によるアジアの国々とのカジュアルな文化交歓(ここには日本の伝統文化を新しい目で受け入れる傾向も含まれる)などの影響を受けている。こうしたものがすべて混ざり合い、互いに影響し合い、そして変化していっており、どれひとつをとっても私たちの日常生活に主要な力を持っているとは言い難い。それはあたかも、日本人は生活の違った部分に合わせて違った文化を使い分けるという特質をもっているかのようである。そしてこの面が典型的に表れているのが私たちの食生活様式と音楽であろう。
スティーゲは「文化とは、人間の共存を可能にし、調整するための習慣や技術の積み重なり」(2002, p.38)と述べている。この意味で、現代日本の多様かつ過渡的な文化層の人間と音楽を通して向き合う職業である音楽療法士は、きわめて複雑な洞察を求められていると言えよう。
私自身は日本に生まれ育ち、社会人となって後にアメリカで4年半にわたって音楽と音楽療法を学び、再び日本で仕事を始めて10年余になる。その中でいつも「日本で音楽療法の仕事をするとはどういうことだろう」と途方に暮れながら道なき道をさまよってきた。この場を借りてそのさまよいを振り返り、臨床的/音楽的、学問的、専門職的という三つの視点から述べてみたい。
3. 日本の音楽療法の臨床的視点
・ 集団と個人の捉え方
まず、臨床的な面で、私が日本の音楽療法の重要なテーマであると感じるのは「集団:個人」の捉え方である。日本の音楽療法にはすぐれた集団セッションが多くあり、伝統的な価値観である「和」を日本人の「健康な在り方」の支えとして活用している。例えば、日本人の集合的アイデンティティとも言える独特のリズムや歌を使っての集団歌唱は、高齢者へのアプローチの定石である。日本人は「集団」というものに対して高く特別な価値を置いており、その情緒的/実際的な歴史は長く、また深い。よって、このテーマを西洋的な音楽療法メソッドによって単純に分析したり結論付けることはできない。日本の音楽療法士の特別な研究と理解が必要とされている部分であろう。
しかし、とくに高度経済成長期以降、「自己表現」や「自己実現」も日本人にとって重要な価値観となり、音楽療法でも小グループや個人セッションが模索されている。その数はまだ決して多いとは言えないし、方法に関してもまだ成熟したとは言えない。欧米のやり方をそのまま持ち込むことが無意味なのは言うまでもない。
よく見ていると、今日の日本人の個人志向の文化は伝統文化から分裂していっているわけではなく、根強い集団主義に基づいている。逆に、一見穏やかな大集団にも個を活かそうとする自己実現のさまざまなうごめきがある。そして健康的にいきいき生きている日本人というのは、このバランスを何らかの形で実感できた人のように見える。反対に、集団が個人を押し潰したり、ゆがんだ個人主義が人と人とのつながりを分断したりという混乱が、しばしば療法テーマの根底に存在する。
集団と個人が発展的に共存していく、ここに日本らしい形で着目するような臨床とはどういうものだろうか。音楽は非常に個人的でもあり非常に社会的でもあり得る媒体として、大いに耕される可能性を持っている。
・言葉や表現の独特の位置付け
それと関連して、私にとって日本文化の謎であることの一つに「言葉や表現の独特な位置付け」というものがある。私が最初に音楽療法を学んだのは英語文化においてであり、そこでは言葉を結論に向けて直線的に論理立てていくために使っていた(図1)。帰国した私が感じた日本文化の言葉の使い方とは、あたかも渦巻きを描くように雰囲気や均衡、美意識などの中をたゆたい、調整するもので、渦巻きの中心に浮かび上がってくる結論に関しては言葉を飲み込んでわかり合おうとする不思議なプロセスであった(図2)。
図1: The Language Process in Western Culture
図2: The Language Process in Japanese Culture
日本人は「言葉を慎む」ことで自己の存在を深く生きようとし、「沈黙している」ことで雄弁な表現をしようとすることがある。こうした傾向はクライエントがその内的世界を言語化するときや、家族が療法の見通しについて言語化するときなどに独特の表れ方をする。日本人にとっては、言ったことやその言い方だけでなく、注意深く言われなかったことや実際に取られた行動も「表現」の一部に含まれるのである。
言うまでもなく、ここで音楽は非言語的媒体としての大きな可能性を持っているが、さらにその音楽というものの中においてさえ、この日本人の特徴は独特の表現の現象を生み出すのではないかと思う。例えば、私は音楽療法士として、脳硬塞の後遺症で言葉のない寝たきりの高齢者への歌いかけをしていたときのことである。この人は限られた表現手段と言語的認知機能の中にあっても、眼球や口の動き、表情、涙などで歌に対するさまざまな感情の変化を見せた。そして印象深かったのは、わきおこる感情を解放するだけでなく、自ら抑制することによっても自分を「表現」をしていると見てとれたことである(生野、2002b)。
西洋の音楽療法理論では「表現すること」を最大の道具あるいは目的とする傾向にあるが、それだけでは割り切れない日本の臨床理論も深められていくべきだと考える。
・ 療法の目的「Doing」的価値と「Being」的価値
次に、専門職としては新顔である音楽療法士として実践の現場に参入していった私自身の経験から、療法の目的ということに触れたい。現場で他の専門職と肩を並べて仕事をしていると、その日の仕事の成果について同じ記録用紙に書き込める場合と書き込めない場合がある。書き込めなかったときは、音楽療法士だけが何か無駄な時間を費やしてしまったようで気が引ける。なぜなのだろうか。私は長い「悩み」の末、あるときからわれわれ音楽療法士の達成を「doing」と「being」に整理して考えるようになった。「doing」の健康とは「機能していなかったことが機能するようになる」「できなかったことができるようになる」「数量的に見て明白な向上を見る」ことであり、一方「being」の健康とは「何かができなくても、機能しないままでも、人間として満ち足りてくる、存在がより健やかになる」というものである。
例えば、かつて私が脳性マヒの子供を受け持ったとき、私は彼の「全体性」(wholeness)にいくつかの違った面からアプローチした。「doing」をめざす活動としては、彼の弾く箇所を組み込んだ曲をピアノ連弾することでリハビリテーションを行なったりした。一方、「being」の活動のひとつとして、私が作曲した歌を私が演奏するという活動を行なったことがある。その歌詞は、言語を持たないこの子供が、自分の歩み、障害、家族について語るという形をとっていた。
ぼくが生まれたのは9年前の秋。
かあさんは、とても楽しみにしてた。
やさしくて、明るくて、がんばり屋のママは、
ぼくを送りだしてくれた、光の中へ。
ぼくの手と足はちょっと動きにくい。
やりたいこと、行きたいとこ、いっぱいあるのに。
ぼくだって歩きたい、ぼくだって走りたい。
ぼくにもたくさんの大きな夢があるのさ。
だけどぼくには車椅子があるし、
ずいぶん強くなって、階段も登れる。
とうさんと、かあさんと、ひろちゃんとぼくとで、
行くよ、どこまでも、行くよ、夢の果てまで。
このセッションにおいて、子供とその母親はセラピストの作った歌を聞いているだけである。歌詞はすべて療法士である私の想像によるものであったから、クライエントは「作曲/創作」の部分にさえ参加していない。そして母子は歌の印象を言語化することもなく、その結果と言えば、子供がこの歌を気に入ったのかしばしばリクエストしたこと、母親が涙をときに涙をぬぐっていた(しかし一言も言わない…日本人の典型的な表現である!)ことくらいである。それでも私は、この活動がありのままの「存在=being」をふたりにもたらし、療法のプロセスにおいてかなり大きな価値があったと考えるのである。
「doing」一辺倒であった日本の医学も、近年「QOL」という考え方を取り入れており、これは上記の概念にとても近いものだと思う。しかし私は音楽療法の中でそれよりもさらに静的というか、内省的なもの、あるいは「無目的」ともいえるものを感じる。日本文化の根底には「目的に向かって生きる」ことだけでなく「生かされる」といった人生観があるからかもしれない。日本の音楽療法は、このdoingとbeingの両方にまたがる人の在り方をもっと積極的に捉え、深め、伝える手段を追求していくべきではないかと思う。
4. 日本の音楽療法の学問的視点
さて、1990年代から2000年初頭の日本の音楽療法の発展の過程で、最も後回しになっているのが学問的領域ではないだろうか。その背景としてひとつ感じることは、日本人は一般に「考え、創造する」ことより「型を受け入れ、習う」ことで成長しようとする習慣があることだ。この教育-学習の姿勢は、われわれ日本人の文化に深く根付いている。例えば、歌舞伎などの日本の伝統芸能の教育制度では、生徒(弟子)は早い年齢から先達の演技を「注意深く見る」ことと「真似る」ことを訓練され、一人前のプロとして本当に認められるまでは、型に疑問をさしはさんだり、自分の様式を創り出したりすることは一種のタブーである。この教育様式は、子供だった私が西洋クラシック音楽を学んだときでさえ前面に押し出されていた。「疑問を持ったり自分勝手な発想をしたりしない」ことは、日本の「教育-学習」文化に暗黙のルールとして浸透しているのである。
教育の場としては比較的新しい音楽療法においてさえ、これは例外ではない。例えば実践現場では、先輩の型を真似て、セッションの外側から整えようとする風潮があり、それが肝心のセッションの意味性に関する思索を遅らせがちであるように思う。学会発表も、療法プロセスの内容そのものを十分に論ずることなく、医科学論文の型を真似することだけに奇妙な自己満足感が感じられるものが多くある。
しかし私は、音楽療法という分野では、まだそうした模倣による伝統的学習様式に堪えるほどの型は確立しておらず、臨床現場の一歩目から「疑問を持ち、未熟なりに自分の考えを構築する」ことが欠かせないと考える。そして学会とは、現場で経験した音楽的人間的できごとを自分の感覚と考えで構築し、議論を起こしていく場であるべきだと思う。
ここに私は大きな課題を感じるわけだが、それはもちろん初心者や学生だけの問題ではない。日本の音楽療法士はそもそも学問的研究の手法を十分に身に付けるチャンスをもたずに来ていることが多く、とくに先程も述べたような日本の音楽療法に独特のテーマについては、ほとんど手法が確立していない。その結果、ベテラン療法士でも現場を深く知れば知るほど、学問領域を遠く感じてしまう矛盾が生まれる。
学問としての音楽療法の発展のためには、既存の学問方法論を身に付けることと同時に、日本の音楽療法現場の日常と遊離しない新しい学問的方法を模索していくことも必須だと考える。
5. 日本の音楽療法の専門職的視点
さて専門職としての音楽療法については、当然のことながら「音楽療法士の地位の確立」、とくに経済的状況についてのテーマが挙がるだろう。日本の音楽療法士のほとんどは非常勤であり、報酬も不安定、あるいはマイナスになることもあるほどで、アルバイトや家族の支援によってなんとか続けている状況が多くある。
一般的に言って、アジアの国々の多くは、欧米とはまた違った意味での「経済中心社会」である。その歴史的背景から、経済成長が第一の、そして早急の優先課題だからである。音楽療法のような分野は「経済的繁栄に貢献しないもの」という偏見の下に軽視されがちであり、社会の中での価値が低い。こうした中で職業として音楽療法に真剣に取り組んでいる者には、社会での高い地位を確立することがさらなる重圧となる。自分自身の生活のためだけでなく、音楽療法という領域自体への責任も感じるからである。
しかし、経済的自立だけが「地位の確立」ではないことも明らかである。専門職としての実力、成熟度はどうだろうか。職業としての外側は整っても、そのかげに空洞化している部分が多々あることも否めない。これに関連して、急速な発展のもう一つのゆがみである教育の現状に触れたい。
日本では1990年後半から音大を中心とした学校が次々と音楽療法を導入し、かつて独学か留学かの選択肢しかなかった頃とくらべると、教育の機会は驚くほど豊かになった。しかしこうした教育ブームの中には、音楽療法の現実を正しく伝えずに学生を集めていたり、教育者としての人材を適切に配置していなかったりして、「営利主義」を疑いたくなるようなものもある。とくにスーパーバイザーの不足は深刻である。
こうした教育のひずみは、現場に返される。一般的に言って、現在の日本では教育機関での音楽療法熱と、現場での音楽療法熱には温度差があるといわざるを得ない。学校を卒業しても音楽療法の仕事につくことができなかったり、現場での厳しい要求に新卒の音楽療法士が対応し切れなかったりということも少なくない。このような状況が続けば、音楽療法士の社会的地位は、今よりももっと危うくなると言わなければならない
地位の確立」のもうひとつのテーマに、国家の力の強さ、つまり官僚主義と、その下でさまざまな政治的決断が情緒的・血縁的しがらみでなされていくという歴史的システムがある。ここでは音楽療法のような新しい領域が地位を得ていくには非常に込み入った障壁がある。
例えば2000年から2004年にかけて、日本音楽療法学会が音楽療法士の国家資格を求めてさかんな活動を行なったが、そこには大変な困難があったと聞いている。そのプロセスの中では、現体制に受け入れてもらうために、音楽療法の定義、つまりアイデンティティそのものさえ変えることを当然のこととして求められた。学会は、これを是とするか非とするかで大論議となった。
6. 結語:社会への新しい価値の提示としての音楽療法
こういった状況で必ず言われるのは「外国と同じようにはいかない、日本社会には日本独特の政治の方法があるのだから」という論理である。しかし、西洋と日本の音楽療法のはざまを歩んで来た者として思うのは、これは「外国に合わせるか、日本に合わせるか」という問題とは少し違うということである。そもそも音楽療法というのは、西洋であろうがアジアであろうが、既存の社会からどこかはみだすような性質を持っており、受け入れられることだけをめざすと、袋小路にあたるように思う。むしろ音楽療法は、既存の社会を揺り動かしていくもの、人間と関わる音楽という、既存の文化にとって新しい価値観、(あるいは深い価値観)の提示をしていくという可能性をはらんでいるのではないか。
そのために、私たち音楽療法士は何が文化特定的な要素で、何が普遍的な要素であるのかを、臨床、学問、専門性のあらゆる分野で時間をかけて洞察していく必要がある。そうすることでこそ、いつの日か、「経済的自立」にとどまらない本当の意味での「自立」が得られるであろう。
References
Ikuno, R. (2002a). Music Therapy Growth in Japan – The Richness and the Confusion of Transition. In Kenny, C. & Stige, B. (Ed.). Contemporary Voices in Music Therapy. Oslo: Unipub Forlag.
Ikuno, R. (2002b). Music as an “Expressive” Therapy. In Kenny, C. & Stige, B. (Ed.). Contemporary Voices in Music Therapy. Oslo: Unipub Forlag.
Sakurabayashi, H. (1993). Ongak-ryoho towa [What is Music Therapy?]. In Sakurabayashi (Ed.). Ongakuryoho Nyumon [Introduction to Music Therapy]. Tokyo: Gendaigeijyutu-sha.
Stige B. (2002). Culture-Centered Music Therapy. NH. Barcelona Publishers.